向精神薬は<時代の病理>を反映する(論文「向精神薬の意味論」より)
先に<時代の病理>と書いたが、それをもう少し丁寧に表現するなら、時代の流れに適応した結果、当初は同時代人に支持・受容されたが、後にその適応の過剰さが仇になって排斥・迫害された自意識が深く絡んだ病理のことである。具体的に例を示した方がいいかもしれない。時代の流れに沿って、それぞれの<時代の病理>の変遷を追ってみたい。
かつて高度成長期にあった日本では、几帳面で生真面目でありながら小心なメランコリー親和型性格が主流を占め、その性格が罹患しやすい単極性うつ病(単にうつ病と呼ばれることが多い)が取り沙汰にされた。禁欲的・同調的ともいえるこのタイプは、滅私奉公かつ時代への恭順が美徳であり、自意識へ固着する傾向が大きかった。さまざまな内的葛藤からくる抑うつ・思考制止などに対し、当時の抗うつ薬(例えばトフラニール・トリプタノールなどの三環系)はよく効いた。また、じっくり寝かせ一旦活動性を下げてから、じわじわ元気を漲らせていくタイプの抗うつ薬であるデジレルやテトラミドなどの四環系も、受け入れられる素地があった。しかし、いずれも服用感が軽いものであるとは言いがたく、さまざまな不快な副作用を甘んじて受けなくてはならず、患者に忍耐が求められた。また同時代にこれらの抗うつ薬と併用されるかたちで多く処方されたベンゾジアゼピン系を中心とする抗不安薬は、不安・焦燥を体よく治める作用があり、自意識の統合・安寧に寄与するものであった。
しかし時代が移り、20世紀末を迎える頃に、自己主張・アイデンティティ確認を是とする状況になってきた。感情を理性的に統御できなくても、「キレる」というマイルドな表現で納得され、いまここにはない「本来の自分探し」の旅に出る者も多く現れるようになった。この環境下では、喜怒哀楽といった情緒的なものをむき出しにすること、すなわち衝動的にキレて、時には解離的になり、我を忘れることすら容認される土壌が作られていった。自意識からの飛翔・離脱こそが、時代のムーブメントになったのである。このような時代に歓迎を受け登場してきたのは、先にも述べたパキシルをはじめとするSSRIであった。今までの憂鬱な自分にサヨナラし、軽やかに生まれ変われるというふれこみで、SSRIは海を渡って日本にやってきたのだった。まさに医用スマートドラッグのような位置づけを得たのであり、日本で登場する前に、インターネットを通じて個人輸入し自家処方に及ぶ者まで出てくる始末だった。SSRIはうつ病のみならず、社会不安障害・パニック障害、それから強迫スペクトラム全般にまで効用があるなどと喧伝され、まさに自意識のしがらみから抜け出し自由に飛びまわれる魔法の薬物であるかのような認識がもたれるようになった。これは患者のみならず精神科医においても同様である。
しかしSSRIといえど完全なる薬ではなかった。とりわけ人気の高いパキシルにおいて、深刻な退薬症状を呈し、服薬をやめるにやめられない患者が相次いだ。パキシルには依存性はないという前情報が与えられていたはずだが、退薬症状がブレーキとなってやめられないこのような場合もやはり依存性があると考えるべきではないのだろうか。自意識の飛翔が果たせず墜落し、閉塞状況でとぐろを巻いたような状態が依存性・嗜癖であるが、これも現代を象徴する病理で、情緒不安定・衝動性・解離性の裏面を成すものである。また、SSRIのルボックスがこの依存性・嗜癖(例えば、過食嘔吐のサイクル)を解くというのである。SSRIの“迎え酒”的治療があるとは、その万能ぶりにめまいさえしそうである。
私は前掲書『精神科のくすりを語ろう』の中で、<「ライフデザインドラッグ」のように薬局などで一般人が買い求め、誰に管理されることもなく随意に服用したり、またあるいは、治療者が処方した薬物を、患者がその本来の治療目的から離れて使用するようになることにより、治療者という直接患者の心身を知る専門家からの服用(使用)のすすめとは関係なく、患者(あるいは一般人)が自ら進んで服用し、やがては耽るようになること>を「嗜薬」と定義づけ、その啓蒙を行おうとした。向精神薬服用の過程で起こりやすい<嗜薬>を避けるためにも、「官能的評価」取り扱いについて留意すべきことを書いたが、ここに再掲したい。
(1)精神科薬物の服薬ないし投薬にあたって、その服薬者に妥当な薬物の判断は、必ず精神科薬物取り扱いのプロである精神科医が行わなくてはならない。服薬者は、あらかじめ精神科医に指示された用法・用量を守る。服薬の結果、身体的・精神的依存性を引き起こしそうならば、必ず投薬判断した精神科医がそのフォローアップを行う。
(2)精神科医ではない一般人が、インターネットなどで好みの薬物を自己購入し、自己服薬に及んだ場合、ここで生成された官能的評価は著しく妥当性を欠くため、取り扱うべきではない。精神科医の処方箋によらず、知人から貰い受けた薬物を勝手に服用した場合も同様である。
(3)収集された官能的評価を検証し編集する、第三者である精神科医は、その官能的評価が(1)(2)の正統な手続きを踏んだものなのか、吟味する必要がある。
ただ、「官能的評価」が健全に集積される状況というのは、精神科医と患者が幸せな治療関係を取り結べている場合においてだけ成立するものであって、そこから逸脱する患者が多くなってくる状況では、このような但書も空文化する。依存性・嗜癖を巡る治療状況はいたちごっこになりやすい。これらは次の時代に、より深刻さを増していくことが予想される。
話を元に戻そう。SSRIが全般に行き渡った状況で、その効能の限界・問題点が明らかになってきた。そして、それとほぼ時を同じくして、衝動性・解離性というものが看過できぬ問題として、時代の前景に浮かび上がってきた。横断的にうつ状態が見出されると、直ちに抗うつ薬(SSRIを含む)を処方する精神科医が圧倒的だった頃にも、単極性うつ病とは違う病状経過を呈する疾患があることに気づいていた精神科医も少なくなかった。ところが、その病理に「双極2型障害」という病名が与えられ人口に膾炙するようになったことにより、ようやく治療法が大きく見直されるようになった。そして、「双極2型障害」において感情調整薬が治療の主役に躍り出てきた。リーマス・デパケン・テグレトールなどである。これらはずっと昔から存在していたが、時を経て存在感を増すことになったのである。さらには、ジプレキサ・セロクエルなど後から登場した抗精神病薬においても、感情調整薬としての効能が“発見”され、さらに適応範囲を広げることとなった。ただ、この感情調整薬について、治療上問題もある。患者の側の受け入れが今ひとつ芳しくないのだ。感情調整薬の治療戦略は、縦断的に躁うつの感情の波を緩和するというものだが、近視眼的に効能を求める患者からはその薬効を実感できないという声が多い。薬圧があまりなく、服用感が少ないため、かえってコンプライアンスが維持しにくいのである。患者が欲しない薬物をどのように納得させて服用維持させるか。パターナリズムがほとんど壊れてしまっている現代において、それは可能なことなのか。またその治療に、普遍的正義ならずともせめて時代の“正義”はあるのか。これらは今後の精神医療における根源的な課題であろう。
熊木徹夫(あいち熊木クリニック<愛知県日進市(名古屋市名東区隣)。心療内科・精神科・漢方外来>:TEL: 0561-75-5707: https://www.dr-kumaki.net/ )
<※参考>
「薬物のばらまき」はなぜ起こるのか ~<身体感覚>を導きの糸として~
「らしさ」の覚知とは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
臨床現場、混乱の原因となるものは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

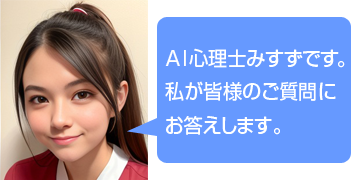

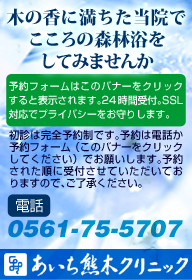



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません