治療戦略的プラセボ ~精神科薬物療法の目指す未来~
1:はじめに
精神医学および精神科薬物療法は、ながらく混沌のなかにあった。それは患者の示す精神症状がどのような体のメカニズムによるものか、うまく描き出せないためであり、またそれゆえに向精神薬が効くのに、どのような薬理学的背景があるのか、うまく説明できないためであった。(向精神薬誕生から50年以上経つのに、それらの薬効にいまだ確たる裏づけが与えられていないことの傍証として、『精神疾患は脳の病気か? ~向精神薬の科学と虚構~』E.S.ヴァレンスタイン(みすず書房)が挙げられる)
精神医学が、脳の科学を志向して、さまざまな精神薬理学的仮説を立て続けることは、それが仮説の域を越えてくることはほとんどないとしても、ひとつの方向として、あながち悪いとは言い切れない。しかしだからといって、薬理学的アプローチ一辺倒で精神科薬物療法を行っていくならば、薬理学的に説明できぬ要素を排除しようという動きばかり際立ち、治療において精神科医・臨床心理士や患者の抱く感覚がないがしろにされることになるだろう。結果として、臨床の地味はやせ衰える一方で、精神科医・臨床心理士および患者にとり、決して豊かな治療環境の到来はないのではないかと危惧する。
では、薬物療法においてどのようなことを意識し、目指していけばよいのか。本論では、そのひとつのあり方を提言したい。
2:精神科患者のまわりにあふれる情報
近年、精神科を訪れる患者とそれを取り巻く情報には、いくつか問題がある。それを以下に挙げてみたい。
患者は、薬物の具体的な効果についてすでに見聞きしたうえで、受診することが多くなった。もちろんそれらは、インターネットなどの口コミ情報を元とした他者の服薬体験記であり、玉石混交なのではあるが、何も情報源がなかった時代とは大きな違いがあるといえる。
そして治療に先立ち、患者はさまざまな副作用情報(なかには非常に偏ったものもある)に触れてしまうことが多く、処方される前からすでに精神科薬物に対してかなり猜疑的になってしまっていることがままある。すなわち「精神科医が薬を、不必要に多く処方するのではないか」「一度服用を始めたら、簡単にやめられないのではないか」「ぼけてしまって、戻らないのではないか」などである。
さらに情報収集の結果、あらかじめ患者自身が自分にふさわしいと思う薬物を選定し、処方を求めてくることも少なくない。もちろん、精神科医と建設的な治療関係を結べるタイプの患者であるならば、この求めに応じてもよい。しかし、なかには特定の薬物に固執し、さらに依存・常習傾向をもつようになる患者もいる。
ともかく、精神科医のみが薬物の情報・知識を占有する時代は終わっているといえよう。
3:これまでにあったプラセボ(偽薬)をめぐる問題
薬物療法のあり方を論ずるにあたって、ここではプラセボ(偽薬)効果について考えてみたい。プラセボは薬効を規定する重大な要素だからである。まず従来からいわれているプラセボを例示し、それぞれについて検討を加えたい。
(1)医薬品開発において治療効果を検証する場合(いわゆる治験)、ダブルブラインドテスト(二重盲検法)が用いられる(※ブラインドテストとは、被験者の思い込みによる影響を確認するため、真薬と偽薬(本来、まったく薬効を持たないはずもの)を投与する被験者グループを用意し、それぞれの被験者には真薬が偽薬かを知らせずに試験を実施し、効果を検証することである。また、試験の直接の実施者が真偽を知っている場合、試験者の挙動が被験者に影響を与える可能性や、試験結果の判定に予断を与える可能性もある。これらの影響を避けるために、試験の直接の実施者にも真薬偽薬の区別を知らせずに試験を行う方法が、ダブルブラインドテストである。[参照:ウィキペディア])。このダブルブラインドテストにおいて、新薬Aを与えられた被験者のうち、50%に薬効が確認され、偽薬Bを与えられた被験者のうち、30%に薬効が確認されたとする。本来、まったく薬効を持たないはずの偽薬Bでなぜ30%もの薬効があるのかと訝る向きがあるかもしれないが、実際これぐらいの割合で偽薬Bに薬効発現が起こるものである。この偽薬Bが引き起こす薬効を指して、プラセボ(偽薬)効果と呼ぶのである。すなわち、新薬Aが本来持つ薬効は、偽薬Bがもたらしたプラセボ効果を差し引いた50-30=20%と考えられる。
このように科学の土俵に乗せて、統計的処理を試みると、人間の体は暗示にかかりやすく不確実なものであり、人間の認識とは、本当に薬効がないものでも偽の”薬効”を感じてしまういい加減なものということになる。そしてプラセボは、正確に薬効をあぶり出すに際して、除外して考えねばならない面倒なものという捉え方をされる。
このように統計的データ処理をする場合、薬効発現を把握するためには明晰に数値化されなくてはならないのは分かる。しかし、実際の臨床現場でただ一人の患者を前においている状況でも、同じように”純粋な薬効”など抽出しうるものであろうか。その時々の患者の体調の変動や、精神科医と患者の関係性といった多くのファクターが薬効の発現を左右するはずなので、実際の薬効というものは、プラセボ効果を差し引けばわかるというほど単純なものではない。
(2)今は減ってきていると思うが、かつて精神科病院では、患者から不眠時の頓服薬の度重なる要求がある場合、患者には内緒で、乳糖など本来睡眠薬としての薬効が期待できないようなものを処方することがあった。実際このようなもので眠りにつけてしまうケースもままある。これもプラセボと表現されるが、これは先に挙げたダブルブラインドテストにおけるプラセボとは意味が異なる。語弊があるかもしれないが、この不眠時薬投与は一種の騙しである。
本当の睡眠薬を処方し続けると、耐薬が起こり、依存症になることもあるので、そのようなことを避けるための苦肉の策というわけである。その背後には、人間は本当に薬効がないものでも、場合によって偽の”薬効”を感じてしまうようないい加減な存在なのだから、本当の薬を与えるまでもない、乳糖でも与えておけばごまかせるのだという考えがある。または、薬物は医師が天下り的に患者に処方するものであって、患者はその薬効などに頓着せず盲目的であるのがよいということになろうか。
これは、昔の一部の精神科病院においてのみ通用したやり方である。患者が薬物情報をふんだんに取り込み、治療に積極的に関わろうとする今の時代にあって、このような昔からの精神科病院的プラセボは、やはり時代錯誤なものである。
以上(1)(2)のように、これまでの精神科臨床において、プラセボには決していいイメージが与えられることはなかった。それゆえ、治療上積極的にプラセボを評価し活かすなどという発想はされてこなかったといえる。
4:「治療戦略的プラセボ」とは何か
かつて私は、拙著『精神科医になる ~患者を<わかる>ということ~』(中央公論新社)のなかで、“処方あるいは服用した薬物について、患者あるいは精神科医の五感を総動員して浮かび上がらせたもの(薬物の”色・味わい”といったもの)や、実際に使用してみた感触(薬効)、治療戦略における布置(他薬物との使い分け)といったもの“を指して、精神科薬物の<官能的評価>と命名した。私は処方行為において、この<官能的評価>が欠かせぬものと考えている。
薬の処方とはすなわち、精神科医が患者の体を介して感じたことを自らの体で再体験しなおすことで完結する行為であり、精神科医の身体感覚がまるで関わってこないような患者への遠隔操作であってはならない。もちろん服薬の当事者は患者であるから、患者の服薬体験(および患者の口から語られた言葉)が治療のすべてのベースになる。患者が十分に薬物についての知識を持つことを助力し、患者自身が薬物を服用してどのようにその効果を感受するのか、そのあり方を教え、そこから発せられる言葉が治療において有益なものとなるように、患者の体と言葉を“開発”していく。その際精神科医も、患者の服薬体験にチューニングするため、自らの感覚を研ぎ澄ますことが必要である。そして精神科医は、患者のなかに発生した”心地よき感覚”を捕まえ、その感覚をさらに膨らませるように働きかけるのである。それは、細かなところにまで神経を通わせて作られた料理の奥深さを味わうのに、十分に繊細な官能を働かせなければならないのと、よく似ている(いうまでもないが、その薬に本来備わっていない薬効を感じさせるよう、暗示にかけるのではない)。その際、患者の感覚をあくまで信頼し、患者に治療のドライブ感を持たせるように配慮する。その上で精神科医は、自らが患者のうちに発現をめざす薬効と、実際に患者が体で感受する薬効を摺り合わせ、最小の薬物で最大の効果を狙うよう仕向けていく。患者の治療着地点(具体的には、服薬しながらの寛解状態、そしてこれが最も重要なのだが、最終的に薬をやめきれた地点)を、なるべく具体的に示し、イメージさせるところまでが理想的な初期治療の流れである。
患者に治療のドライブ感を持たせ、薬効の感受・言語化を助力し、最小の薬物で最大の効果が得られるよう仕向けていくという、この一連の過程で特筆すべきなのは、薬物のポテンシャルを増大させていることである。本来その薬物に期待される“標準的薬効”以上のものを有効に発現させることこそ、精神科医の本領である。それは、適切な薬物の選択を行うことに勝るとも劣らぬ精神科治療の要諦である。この際、精神科医が治療上果たすべき役割とは、“指揮者”“映画監督”“編集者”などになぞらえられるものである。この過程で精神科医が導き出している“薬効”は、実際には意識されることが難しく、よって言語化することがかなわぬことが多い。しかし私は、この“潜在的薬効”こそ精神科医という専門家が治療に介在していることの証しであり、これを顕在化させようとする営為こそ、治療の縦断的(歴史的)・横断的(空間的)集積を果たしていく上で欠かせぬものだと考える。それゆえ、この“潜在的薬効”を「治療戦略的プラセボ」と命名し、その意義について言及することにしたい。“治療戦略的”とするのは、従来からいわれているプラセボと異なり、治療に積極的な働きかけができ、戦略的にその発現をコントロールしうるという意味においてである。
またこれまで、精神科医と患者が織りなす薬物療法において「治療戦略的プラセボ」を説明してきたが、これはつまるところ“薬物を介した精神療法”なのであるから、精神科医が臨床心理士・看護師をはじめとするコメディカルと治療的連携(チーム医療)を行うのにも非常に有益である。ある薬物の狙うべき効果に仮託して、治療の意図を伝達できる。薬物は恒常的に組成の変わらない物質なので、精神科治療における標準的媒介物となりうる。この際、自ら処方経験を持たない臨床心理士は尻ごみすることがあるかもしれないが、心配は無用である。ある処方の前後で、ある患者がどのように変わるか、その推移を言語的に抽出できる力を持つものであれば、薬効はそこから逆にあぶり出すことができる。その言語的抽出の繰り返しで薬物の特性をつかむことができるようになり、さらには「治療戦略的プラセボ」の演出に一役買うことさえできるようになる。そこでの治療チーム内での共通言語は<官能的評価>である。どのような職種の人々も、薬物に絡むことを忌避せず、薬物を同じ土俵で語り、「治療戦略的プラセボ」を働かすことに興味を持ってもらうことこそ私が願うところである。
5:身体感覚と「治療戦略的プラセボ」
近頃臨床の現場で、インフォームド・コンセントという言葉がよく用いられる。これは、今後の治療展開で想定されうる良くない事態を、治療者が事前に患者に話して聞かせ、了承を取り付けておくというものである。ここで交わされるのは、治療の言葉ではなく、契約の言葉である。治療者の責任回避・防衛のための言葉といってもよい。それは残念ながら、<治療者=患者>間の関係や治療そのものを豊かなものにする言葉ではなく、「治療戦略的プラセボ」を膨らませるのに役立つ言葉でもない。予想される薬物の副作用の伝達・了承も、それがもし治療者の責任回避を旨とするなら広い意味でのインフォームド・コンセントになるが、患者がつまづくかもしれない障壁をあらかじめ知らせ、治療の可能性がしぼまないようにとの配慮に満ちたものであるなら、これは「治療戦略的プラセボ」に資する言葉だといえる。その違いは、治療の可能性をふくらませるか否かである。それから、伝えるべき副作用情報は患者に応じて変えなければならない。これもまた治療の可能性を限局せぬように配慮したいのだが、その加減を決するのは難しく、これ自体が治療の腕を示すといってもよい。
また精神科臨床現場で、極端に薬物を嫌い何が何でも服用を避けようとする患者や、それとは逆にまるで頓着せずに薬物を受け入れ、精神科医の指示を超えていささか過剰に服用してしまう患者に遭遇することがある。双方はまったく逆のタイプにみえるが、私は表裏一体のものだと考えている。どちらも身体感覚が生来的に鈍いか育ってきておらず、薬物について適切に官能を働かせ受け入れていくことができない。薬物という異物と折れあうためには、ある程度身体感覚の訓練が要るのである。それに、本来その薬物に備わっていないはずの薬効を感じたり、また特別暗示にかかりやすいタイプの患者も同様である。こういった患者のうちに「治療戦略的プラセボ」を生み出すには、より多くの困難が伴う。
以上のことから、薬物に対し精神的依存がつきやすい患者も、当然のことながら身体感覚が鈍いタイプであるといえるが、もうひとつ注意しなければならぬことがある。それは「治療戦略的プラセボ」形成を阻害する治療者の貧しい言葉も、患者の薬物依存を助長するということである。すなわち薬物依存とは、身体感覚が鈍くそれに根差す言葉の乏しい治療者と患者による“合作”なのである。薬物依存とは、ひとりその当事者だけの問題に帰着させることはできないのだ。それゆえ薬物を扱う者は、自らの身体感覚を磨き、他者の身体感覚をも開発し、それらを互いにすり合わせ、最終的に服用者の納得に導く責任を負うのだと肝に銘じておきたい。
熊木徹夫(あいち熊木クリニック<愛知県日進市(名古屋市名東区隣)。心療内科・精神科・漢方外来>:TEL: 0561-75-5707: https://www.dr-kumaki.net/ )
<※参考>
「薬物のばらまき」はなぜ起こるのか ~<身体感覚>を導きの糸として~
「らしさ」の覚知とは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
臨床現場、混乱の原因となるものは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
初診時における精神活動(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

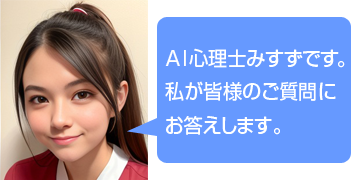


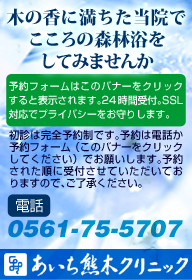



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません