初診時における精神活動(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
初診においては、前情報があるときもあれば、ないときもある。ここでは一応、前情報はないものとして話を進めたい。また、患者が単独で来院する場合も多いのだが、ここでは患者以外に家族が一人帯同するケースで考えてみることにしたい。
まず患者が入室するとき、その様子から一瞬にして何かを“嗅ぎ分ける”ことが極めて重要である。患者当人の見目かたちや佇まいは元より、一緒に入室する家族の立ち居振る舞い、もっというならそこに醸し出される空気のような、言葉では表わしがたいものまで感じるのである(ただ、じろじろ見るのとは違う)。
そして、挨拶を交わす。「あなたが●●さん(患者の名前)ですか。どうぞこちらにお掛け下さい。あっ、お父さんもご一緒ですか。こちらに座っていただいてもよろしいでしょうか」というような具合である。そして、「初めまして、私は熊木と申します。どうぞよろしくお願いします。」と名乗るが、そのときにようやく患者と目を合わす。なぜそれまで患者の目を見ないのかというと、患者によっては対人恐怖の強い人がいて、初対面の精神科医が意味もなくじろじろ見ているような素振りをすれば、身を縮こまらせ、胸襟を開こうとしてはくれなくなることがあるからである。また目を見るといっても、患者の瞳のやや下を見ていることが多い。これも同様の事情からである。
そこでしばらく、世間話をし、場合によっては「よく勇気を持ってここに来られましたね」と労いの言葉をかけることもある。労いが必要か否か、家族の様子を見ていると分かる。家族が苦渋に満ちた表情で押し黙っているような場合には、来院にあたり一方ならず葛藤を孕んだいきさつがあると見るべきである。患者を労うことで、間接的に家族をも労うことができれば、とも考えている。
そしていよいよ患者の主訴を訊くことになる。患者が自らに何ら問題を感じていず、家族に伴われ不承不承来院に応じてきている場合は、まず家族が問題だと考えていることを訊く。その過程で、それとなく双方の表情を見比べてみる。表情こそ、実情を一番雄弁に物語る。
また患者であれ、家族であれ、彼らの語ることをそのまま受け売ることなく、頭の片隅に一旦留保しながら訊いていく。今訊いたことをカルテに書き下すまでに、およそ5分の時間差を与える。すなわち、訊いていくのと併行して、生活歴・既往歴・病歴を私自身のなかで再構築していくような編集作業も行うのである。この時間差を保ちつつ診療を進めていくことは、最も重要なのであるが、実際行うことは存外難しい。だが、これは不断の努力を重ねれば、2~3年で出来るようになる。
病歴の編集を経るうちに、患者や家族が問題とはしていないが、ここを何とかしなければ先に進まない本質的問題に行き当たる。そこで、ある程度双方の話を訊いたあと、私の見立てをおもむろに切り出す。その内容が、患者自身でなくとも、家族に首肯されるようなら、治療の第一段階クリアといえる。そして今後の治療方針を伝える。私は何を目指しているか、それは患者ないし家族のどのようなニーズに応えうるものであるか。薬物を選択するなら、以下のことを伝える。その処方根拠、そして予想される副作用で頻繁に見受けられるものと、かなりまれだが注意を要する重症のものとを。
このなかで一番大切なのが、私の治療指針と患者ニーズの摺り合わせである。互いの目指す方向が一致をみれば、それだけで今後の治療展開につき楽観的になれる。しかし、互いの目指す方向にかなりのずれがあるならば、今後の難航を覚悟しなくてはならない。初診40分の最後の山場が、この治療契約を行うところである。これまでの40分にわたる診療経過はすべて、ここでうまく患者(および家族)の納得・合意に落とし込むため、展開されてきたものといっても過言ではない。
~~~~~~
以上が初診において私が行っていることの概要である。ここからは、その初診のプロセスにおける私のうちなる精神活動を素描することを試みたい。
先述したこの患者についての本質的問題と治療指針に辿り着くために、どのような思考を繰り広げているのか。それは、めくるめく推理の連続と言っていい。具体的にいうなら、時々刻々姿かたちを変容させる眼前の患者の有りように意識を添わせ続け、患者という存在構造が指し示すベクトルを感知し続ける。それは、精神科医の中井久夫が統合失調症患者の認知特性として提唱した「徴候空間=微分回路的認知」(『分裂病と人類』東京大学出版会)と同質のものでなくてはならない。
そして、その認知の過程で参照枠となるのが、これまでに同様の営為のもと集積されてきた治療経験である。“かつて見た(診た)何もの(誰)か”を想起し、眼前の患者とのアナロジカルな照合を行い、“どこがどう似ていて、どこがどう違うのか”を検証する。さらに、かつての治療経験が今回においても援用できうるのか、決断しなくてはならない。もしかつての例とは似て非なるものであるならば、何か別の足掛かりを見つけ、新たな治療法を即時に創案しなくてはならない。
ここまでは、初診の診療過程で、連続的に思考していくことを強調してきたが、どうしても付言しておかなくてはならぬことがある。極論するならば、精神科臨床における洞察では、出会って最初の1分がすべてである。もっというなら、患者が診察室に入室してから挨拶を終えるまでの10秒こそが、極めて重要である。
これまでの記述に対し逆説的だと思われるかもしれないが、よくご覧いただきたい。私は、「精神科臨床では、出会って最初の1分がすべてである」と言っているのではなく、「精神科臨床における洞察では」と言っているのである。精神科医の神田橋條治は、講演会や症例検討会など各所で、“フラクタル”という言葉をよく持ち出す。これは診療過程におけるほんのちょっとした断片のどれを取り出しても、その過程全体と相似形を成していることを説明する際、使われる表現である。そう、最初の10秒や1分の中にも、すでにフラクタルが現れていて、診療をかなり進めてから見返してみると、「ああ、あの時すでに・・」と膝を打つことが実に多いのである。
先述した診療過程をフラクタルの視点から読み替えてみると、以下のようになる。診療過程の断片を示されたとき、そこから全体を指し示す可能性を持つフラクタルを炙り出し、それに基づき「こうくるなら、こうでなくてはならないはず」と想像を逞しくして推理をおこない、さらに何に着目するか決定を下しつつ、質疑応答を繰り返していく。すなわち、フラクタルの見いだしを手掛かりとして、その10秒という断片を押し広げていく作業こそが、初診40分のなかで行われているのである。
たった10秒・1分といえど、重要な情報が開示され、そのたびに見立てが微少な軌道修正を受けていく。しかし、最後には最初に読み解いたフラクタルのなかに内在していた基本的問題に帰着する、そのようなイメージである。
したがって、最初の1分でわからないものは、時間を十分にかけたからといって、分かるようになるとは限らない。大抵の場合、1分で分からないものは、私にとり難治なものであるか、あるいはそもそも治療の必要性がないものであることが多いようである。これはレトロスペクティブに治療経過を見返したときに、よく気づかされることである。
熊木徹夫(あいち熊木クリニック<愛知県日進市(名古屋市名東区隣)。心療内科・精神科・漢方外来>:TEL: 0561-75-5707: https://www.dr-kumaki.net/ )
<※参考>
「薬物のばらまき」はなぜ起こるのか ~<身体感覚>を導きの糸として~
「らしさ」の覚知とは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
臨床現場、混乱の原因となるものは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

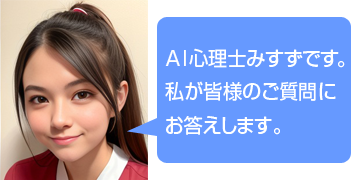

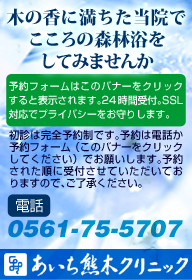



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません