中井久夫随想~論文「薬物使用の原則と体験としての服薬」をめぐって~
中井久夫には多彩な貌がある。臨床家(精神科医)・医学研究者・訳詩家・詩人・エッセイストなど。そのいずれにも共通するのは、実践家であり体験の伝承者であるということ。評者は中井と同じく精神科医であるが、その経験年数において多大な格差がある。よって、中井の精神医学の経験を恭しく拝受するべきなのかもしれないが、今回はあえて評者自身の体験と見比べることで、中井の臨床家としての一側面を浮き彫りにし、その上で人間中井久夫を抽象することに臨みたい。おそらく中井自身がその体験をそのまま無批判に後輩が受け取ることを望んでいないと考えられること、体験の伝承者である中井を論ずるにはこのアプローチしかないだろうことがその理由である。
中井がこれまで著したものは数知れないが、今回は「薬物使用の原則と体験としての服薬」(『治療の聲』一巻二号、1998)という論文を導きの糸としていきたい。これは中井の書いたもののなかで、とりわけ有名なものではないが、評者が多大な感化を受けたものであるということ、また今見返してみても薬物を論じたものとして類を見ないものであり、ある意味“中井らしさ”が集約されているものだと感じられるからである(中井のオリジナルの文章を取り上げ、それに評者がコメントを加えていきたい。引用文が多いのは、中井の文章そのものを味読していただきたいためである)。
<私は回復期において、原則として賦活を目標としては薬物を使用しない。賦活は自然賦活を最良とする。しばしば「修理途中の自転車にロケット・エンジンを付けて走らせようとする」人があるが、長期的には決して実らず、しばしば端的に破壊的である。「医師は何よりも先ず慎重でなくてはならない」>
<医師の人柄を鑑定し、合格すれば、どんな処方でも受け入れるが、そうでなければコンプラインスを維持しない人、すなわち、「医師が最良の薬である」という格言がもっとも妥当する患者であるか。この場合、慎重性がもっともよく評価され、自慢がもっとも低く評価される。そのために初回に処方しないことさえあり、たいていは二日の処方で、(「眠れなければ翌日おいで下さい」と言い添えて)一日おいて会う(もし眠りがどっと出れば翌日の来院は有害性のほうが高い)>
処方は慎重を旨とすべし、というのは精神科臨床の基本中の基本である。しかし、それを常に胸に留め、実践するのはとても難しいことである。中井の精神科臨床についての知恵の数々に接するときにも、この基本を踏まえていなくてはならない。評者も、医療および医師というもの全般にわたって猜疑心を漲らせている患者には、まず己を信用してもらうことに専心する。そして、その評価をその場では要求せず、いったん自宅に帰って「もう一度来院して、この医師に心身を委ねていいか、考えてきてもらう」ということをよくする。医療の専門家ではない患者であるが、原則としてその患者が医療の流れを主導すること、それに脇から力を添えるのが医師の本来的な役目であることを痛感したのは、中井の文章に出会ったためである。「たいていは二日の処方で、一日おいて会う」という細部にまで込められた配慮も、いかにも中井らしいものである。
<すべての場合に重要なことは、患者が薬物の作用に「賛成」するように持ってゆくことである(私が「受容」といわないことに注意してほしい)>
<患者に「服薬感覚」を聞くことが必要である。これは、治療に患者が参加する第一歩である。その際に回復過程の初期には、薬物効果に対するアレキシシミア(感情失読症)がありうることを考慮すべきである。サリヴァンによれば、自己身体の辺縁的感覚の回復が急性精神病状態からの回復において最初に患者に期待しうることである。これはアレキシシミア回復の第一歩となりうるので、服薬感覚を問うことは、そのためにも重要である。また、患者の服薬感覚は多く実態に即しており、患者が合わないという薬は先ず「ほんとうに合っていないのではないか」と医師自らが疑うことが必要である。この反省は、患者に伝わって治療関係に寄与する>
<一般に、薬物は常に医師とその言葉とともに処方されなければならない。薬ののみごこちは決して聞きわすれてはならない>
<私は、新薬は使用に先立ってほとんど必ず自己服用をしてきた。(中略)
私はまた、臨床において、常に「薬ののみごこち」を患者に聞くようにしてきた。(中略)
自己服薬体験と患者の「のみごこち」報告という、この二つのデータを交えつつ、薬物使用体験とする。これは科学論文を目指してはいない。(中略)私の目指すのはむしろ、江戸期の篤農家の実践的な「農書」である。あれは日本的なプラグマティズムの一つのモデルである>
ここにあるように、「薬ののみごこち」を患者から聞くというのは、あらかじめアレキシシミア傾向にある患者が、回復の足がかりを得るためにそれが欠かせぬものであるからであり、また患者が薬物の作用に「賛成」するように持ってゆく前提として、患者によって治療における主体性の獲得がなされていなければならないからである。「薬ののみごこち」を了解し言語化する作業は、慣れない人にとって存外難しい作業なのだが、いったん言葉を紡ぎだせるようになると、今受けている治療のプロセス、ひいては薬に様々なかたちで反応している自らの身体のありようについて自覚的になることができ、治療(および治療関係)がドラスティックに変わりうるのである(私事であるが、評者はこの「薬ののみごこち」の重要性を強く信じたことから、『精神科のくすりを語ろう~患者からみた官能的評価ハンドブック~』および『精神科薬物治療を語ろう~精神科医からみた官能的評価~』の2冊(ともに日本評論社、後者は共著)を上梓することになったのである)。
<慢性分裂病状態においては、症状を標的とせず、身体および生活の全体を標的とする。多くの症状は、皮膚炎におけるカサブタのように保護的である。これを強引に奪うことはカサブタを剥がすに等しく、われわれは基本的には自然脱落を待つべきである>
<私の考えでは、薬物の標的となるものは、恐怖であり、不安であり、その背後にある精神、自律神経系、内分泌の超限的興奮あるいはその遷延膠着状態、要するに生体の心身の全体であって、決して診断の手がかりである特異症状ではない>
「薬物療法においては、疾患が呈する特異症状を、直接の標的としてはならない」という教えである。評者はかつて、中井の直弟子である先輩精神科医から、「薬物は症状ではなく<構造>に効く」と聞かされ、深く感じ入ったものだが、それは同じ内容を指し示していると考えられる。“生体の心身の全体”や<構造>はまったく抽象的に見えて、とりとめないものであるが、その存在を想定し薬物療法に取り組むのでなければ、決して薬物療法はうまくならないし、ちょっとした変化球がきたときに、とっさのアドリブがきかないものである。
<私はしばしば、患者に「このクスリでひょっとしたら治るかもしれないが、ほんとうに治ってもいいかい」「長年親しんだ症状はたとえ多少不愉快でも別れると淋しいものだよ、耐えられる?」とくどく言う。そう言って「大丈夫です」と真実味のある答えを何度も聞いてから初めて処方する>
<症状を薬物によって有無を言わさずに奪われた時の空虚と索漠とを医師は知らなければならない。また、症状がある時にはない不安として症状が不意に再来しないかという不安がある。この不安だけは(特に幻聴)が存在する時にはないもので、症状下に少しだけ患者はほっとする>
症状というのは一概に“打ちのめすべき、にっくき敵“とは言い切れず、時として自我親和的なものとなりえ、やがて”腐れ縁“ができてしまうこともある。こういう考え方は、ただ病邪をたたくことに専心する西洋医学的思想の単純さからでは決して発想されることはないものである。”幻聴があれば幻聴という症状が発生してくることを憂慮することがなくなるので、これが患者の救いになる”などというような懐深さは、それこそ長年にわたり病邪に心身を支配され苦しめられている患者の人生にも、暖かい希望のともしびを与えるものである。
<古く米国近代医学の父サー・ウィリアム・オスラーのいうごとくヒトは薬物をねだる(crave)する動物であるが、同時に薬物を恐怖する動物でもある。このことを念頭に置く必要がある。人間は、症状にかんしても薬物にかんしても両義的である。すなわち「効くクスリは怖い」「効かないクスリはいらない」のである>
<薬圧(中井)による不快感の場合、当然、患者は抵抗し、コンプライアンスが下がるか、大量喫煙あるいは大量水分摂取で対抗する。ニコチンは抗精神病薬の効力を時には三分の一に下げる。薬に種類だけでなく個体差もある。医師に告げずに禁煙して失神した自験例がある。また私自身実験的自己服薬の場合に大量の水摂取で苦痛から脱出しえた。もし私が大量の処方を強いられて逃れようのない場合には必ずこの対処行動を取るであろう。私はこれに「味を占めた」からである。多くの水中毒の始まりはこれではないか。(中略)
服薬を遵守している場合も油断はできない。患者は強迫的心性あるいは医師に対する一種の意地(受け身的攻撃性)を以て長期にわたって大量服薬を自己に強いる場合がある。このような自虐的な例に症例検討会で遭遇するのは、私の実に悲しい体験である>
患者の薬物への対処行動のなかに透見できる複雑な心理について語られている。薬物には投与者(医師)がいて、服用者(患者)がいる以上、その薬効は純粋に生理学的・薬理学的にだけでは説明することができない。私はかねがね「精神療法を行うには生物学的背景を意識し、薬物療法を行うには心理的・生活史的背景を意識して」ということを行っているが、これはあまのじゃくなのではなく、ゆえあってのことなのである。服薬にあたって、薬効に<賛成>させるということは、いかに大切なことか、そしていかに難しいことであるか。
<「彷徨的処方行動」に類したものには状態の些細な変化に応じて薬物の量や種類を変える「過剰対応処方」もある。これは熱心で誠実で小心な医師が起こしやすく、また、治療を焦る患者、紹介患者、診断が難しい患者、回診などで上級医師から治療圧力を医師が受ける患者に起こりやすい。これは患者が「医師はある状態を非としてこれを殲滅させようとしている」と恐れ、「この状態は否定されるべき状態らしいが自分で消滅させようと思ってもできない、さあどうしよう」と無力感に陥れて途方に暮れさせ、さらには「医師は私(の症状)を処罰しようと手を替え品を替えて迫ってくる」と感じて追い詰められる場面さえ考えられる。治療はいちいちの症状を別々の薬でしらみつぶしにするものではない。薬物にはそれぞれの個性があるけれども、当り前の話であるが、いずれも患者の心身全体に効くのである。そしてのみ心地がよい時、また患者が<賛成>できる変化がいつのまにかもたらさせているのを患者がふっと気づく時、薬は少量で効き、コンプライアンスはよくなり、そして片々たる症状はいちいち「捜索殲滅作戦」などしなくてもいつのまにか消失しているものである。薬が合ったという感覚は医師の側にも「何かつかえていたものが流れ出した」という治療感覚となって実感されると私は思う>
<しばしば、改善を認めれば、「朧を得て直ちに蜀を望む」ことになりがちである。すなわち、ただちに薬を増やしていっそうの改善を狙うが、これは不安定性を増大させて、治療がふりだしに戻る確率が多い。また、これは医師が改善をあせっているというメッセージを患者に伝えて、患者をいっそうあせらせる。一般に処方行動は医師のたいていの言よりも患者にとって信頼性の高いメッセージである。心しなければならない。逆に、改善をみたら直ちに減薬する医師もある。これは薬によってようやく獲得した安定を放棄することになることが多い。これは薬を悪として処方行動を「うしろめたく」思う「良心的」医師の落とし穴の一つである>
こちらは、処方者である精神科医の心理、とりがちな行動について触れられている。精神科医である評者は、これらのいちいちに深く首肯しないわけにいかない。これらの微視的・虫瞰的な観察は、まったく驚くべきものである。ここにもあるように、個々の患者に対する処方内容の遍歴ほど、その医師の意図・葛藤・迷い・腕を余すところなく表現しているものは他にない。逐一の紹介状にある曖昧にぼかされた、奥歯にものが挟まったような物言いより、よほど信頼できる情報である。また、それだけ処方というものが明かす事柄があからさまなだけに、医師はそれが他の医師に伝わることに、若干の怯えと緊張があるものである。ところで、評者はこれまでに幾度か紹介状のなかで、意図が判然としない、大層な混乱ぶりを示した処方に出合ったことがある。そのたびに「あなたも、前の先生もかなり苦労してこられたのですね」といって、患者に涙されたことがある。患者は治療が迷走していても、前医に恨み言ひとつ言うことはなかった。苦労を重ねた同行二人、やはりその歩みを尊重しなくてはならない。
<医師に限らず、権威的強制を何よりも嫌う人であるか。(中略)ひそかに薬を減らす実験を時々しているフシがあっても知らんプリをしていてよい。困れば必ず来るからである。こういう人はしばしば「医師を出し抜いて治りたい」と思っており、それがこういう人の治癒へのよい動機づけであって、医師は決してとがめず、「出し抜かれ」れば「やられた」と大笑すればよい。私の経験では強迫症で治癒した場合に、この例が多い>
<薬に限らず、何より「小鳥のように」おびえる人であるか。(中略)まさかと思われるかもしれないが、医師に対して明日は何を話そうか、何を聞かれるだろうか、そういう時にどう答えようかと思って、眠れない患者は意外に多い。宮崎隆吉の報告したところによれば一~二週ごとに全不眠を起こしている例の約半数は「面接前夜の緊張性不眠」である。必ず「みやげを考えずに手ぶらでいらっしゃい」と言っておくことが必要である>
<強迫症はもっとも薬物が効果を奏する神経症圏の障害であるが(中略)服薬を始めたら治療は第一の関門を越えたということである。なぜなら、薬物という得体の知れない汚染物を体内に摂取することを許し、その作用に身を委ねることをみずからに許したからである。そうして、何ものかに「ゆだねる」ことは強迫症から抜け出すためにぜひとも獲得しなければならない姿勢だからである>
患者のタイプごとに、対処法を講じられている。ここには診察室の外での患者の行動に注意が払われている。飼いならされた犬のような忠実な患者を良しとする権威的な医師なら、面を食らうであろう。患者のささやかな“たくらみ”や“悩み”に思いを馳せ、そこに寄せるまなざしは本当に暖かい。最後の強迫症患者の服薬受容についての記載を読んで、評者も思い浮かべたことがある。これは幻覚妄想がある統合失調症患者の例であったが、リスペリドンを用いて直接的に症状を軽減し患者が楽になるようにと狙ったところ、症状は軽減したもののその変化を受け入れられず、結局断薬に到ってしまった。その後、この変化自体への恐れを軽減しようとフルボキサミンを処方したところ、こちらの方が楽になったとして結果先のリスペリドンも服用できるようになったのである。この場合、リスペリドンは北風、フルボキサミンは太陽になぞらえられようか。患者が薬物およびそれがもたらす変化に身を「ゆだねる」ことができるようになることこそ、極めて重要な治療の転換点なのだと痛感する。
<私は特に神戸大学在任中、他院からの紹介患者を引き受けることが少なくなかったが、精神病院よりの紹介患者の処方はしばしば二ページにわたるものであった!こういう場合、だいたい一年にわたる減種減量計画を樹てるのであるが、どれも不可欠で、どれが消去可能であるかは「棒を立てて石で囲み、ある石を取って棒を倒した者が負け」という遊びに似て、まことにスリルのあることであった。
しかし、一見矛盾するようであるが、私は目に見えて間違っており、現に患者の苦悩を生んでいることが明らかな誤処方を例外として、決して、前医の処方を、薬理学的な高みから直ちに変更することはしない。いかに奇異な処方も前医の多年の苦心の結果である。前医の処方を尊重する姿勢は、現医の信用につながる>
<かつて九州大学は抗精神病薬、特に時にレボメプロマジン(LP)の二g/日に及ぶ大量処方を行う傾向があった。これが今も行われているかどうかは詳らかではないが、単味大量療法方式をとったのは日本ではおそらく唯一、九州大学である。これに対して他の諸大学は多剤各少量処方の傾向があった。精神科医の処方行動も文化であるという例である。(中略)かつて九州大学の医師の処方行動をそっと観察したところでは、この方式はきめ細かな増減量に支えられていた。私はその合理性を知った。(中略)私もクロルプロマジン(CP)七五〇mgまで錯乱を続けていた患者が八〇〇mgで嵐が青空に変わるような変化を生じた経験がある>
中井は、直接自らが知らない治療文化についても、偏見をもたず、つぶさに観察する度量を持ち合わせている。またそれゆえ、新たな発見もあるし、別の可能性も開けてくるのであろう。治療文化を歴史的・地理的に相対化することは、自らの体験も相対化しなくてはならず、また全てを受け入れる柔軟性と圧倒的な学識がなくてはならない。それらの資質を兼ね備えた中井は、現代において稀有な精神科医である。
余談であるが、精神病院から時折送られてくる患者の処方は、その種類の多さ・分量の大きさにおいて、本当に驚くべきものがある。ただ評者には数年間精神病院での勤務経験もあるから、その歴史的経緯について斟酌すべき点もあり、荒唐無稽と言い切れない部分もあると感じている。とはいえ、これまで堆積されたその処方に果敢に挑み、減薬を試みたことも一度や二度でなく、大抵ははじき返され、ある程度までうまく減らせたことは稀であった。いつも減薬の際、病棟看護師に「積みあがった将棋の駒を崩落させずにひとつひとつ抜き取る作業をするから、心しておいてほしい」と了解を求めたものだった。比喩は違うが、中井が話していることと中身は同じである。考古学者が古代の埋没品を堆積層から取り出すときは、このようなものであろうかと感じる日々だった。
<私はこの薬(クロールプロマジン:CP)に最初に接したのは治験の被験者としてであるが、12.5mg錠剤内服で、苔寺の庭にような風景が目に浮かび、冷え冷えして醒めた心境になり、感情の振幅が狭くなったことを記憶している。その数年前の座禅経験を思わせるものがあった。次の機会は、三十二歳の時で、虫垂炎手術の術前処置として筋肉注射された。不安が軽くなり、「まあ、いいや、まかせる、どうにでもなれ」という気持ちになった。三度目の自己服薬は一九七九年で、二晩にわたって文章を書きつづけ(『西欧精神医学背景史』であった)、過覚醒になって頭の中がざわざわした。この時、CP一〇mgを内服すると、約十五分で一切の思考が停止した。これは苦しいものであって、無理にものを考えようとしても全然できなかった。患者が稀に抗精神病薬によって「白痴(ママ)にされた」と抗議するのは、これだと覚った。次いで思考はグリセリンのような粘稠な液体の中でもがく人のように苦しいながらも再開してきた。私は頭の中に血中濃度の減衰曲線のイメージを描きながら時間の経つのをひたすら待った。一時間後には思考がほぼ自由になった。過覚醒状態は消えていた。思考だけでなく感覚も身体にも自由感が戻り、周囲を新しい眼で見る思いであった。この経緯を最初の服薬時に患者に話すことがある>
<私がかつてアルコール症の治療に関与していたころ、レボメプロマジンの少量(5~20mg)を使用していた。その理由は、この薬物の特異的な点は「眼の前にあるか手をのばせば取れるようなものに対して我慢すること」を楽にさせてくれるからである。一言にしていえば「おあずけ」が楽になるのである>
<ヒドロキシジン五mgの自己服薬体験では、軽い薬物譫妄状態もあるが、印象的なのは、道路を横断する時、自動車が向かってくるのに「よけなければならない」ことを意識しつつ行動に移せないことであった。一般に、この薬の存在下では、攻撃性や破壊性は意識に上るけれども実行に移せないのではないかと思った。なお、私が二五mgを服薬した時には、ただただ泥のような眠りに落ち込み、目覚め心地はヘドロをかきわけて上に出ようともがく感じだった。攻撃性の強い患者と適応のある皮膚科患者とで一〇〇mg以上、時には二五〇mgでけろりとしている人がいるのがふしぎである。同じく外胚葉である脳と皮膚との共通の問題であろうか>
<(リスペリドンは)新味がない薬のように見えた。ところが、午後になって、私の机の上に「返事を書く気が進まないために何日も積んである手紙類」に対して次々に返事を書いている自分に気づいた。これは「嫌なことができるようになる薬」であった。正確にいえば「すれば事態が進行したり心理的あるいは現実的に良い報酬があるが引き止める気持ちもあってしたくない成分がある行動をするほうに踏み切らせる薬」である。「心理的静摩擦」を下げる薬であると言ってもよかろう。(中略)
「引き止める気持ちがあって、できればしたくない行動」の一つに自殺がある。果して自殺例が出て警告書がまわるようになった。(中略)
「行動への静摩擦を軽減する薬」「着手困難を乗り切らせる薬」としてユニークであると私は思うが、行動というものはそれこそ千差万別であるから、患者の行動全スペクトルの予測を必要とする。ベテランが慎重に使用する薬だと私は思う>
中井自身の服薬体験が生々しく語られている。評者はこれ(精神科薬物の主観的服薬・投薬体験)を<官能的評価>と呼んでいるが、体感をここまで精妙に表現しうる力は中井に特別なものであって、誰にでも求めることのできるものではない。評者はこの中井の<官能的評価>を参照しながら、実際の臨床現場で、薬物と患者の理解に努めてきたところがあるが、それらは幾度となく多大な力を発揮した。その後評者は、さまざまな人々(精神科医および患者)の<官能的評価>を収集し、そしてその編集に数年を費やしてきたが、それというのも圧倒的な感化力をもつこの中井の<官能的評価>と出合っておればこそである。<官能的評価>は何も努力せずとも自ずと生まれるようなものではない。その生成については、さまざまな精神力動を言語化できる思考の強靭さ・感受性の鋭さ・特有の言語感覚を要する。すなわち臨床力が試される。後世に大きな影響を与えうるこれだけの<官能的評価>こそが、何よりも中井の臨床力の証左であるというべきだろう。
本論では、中井の特色・魅力を凝縮したものとして、「薬物使用の原則と体験としての服薬」を取り上げた。本論に眼をとおされた読者には、ぜひ一度、この原著にあたってみてほしい。評者は、現在の日本の精神医療があまりに<官能>を廃絶したものになって、索漠とした情景を呈していることを憂えており、今後の精神医療の行く末が現時点のベクトルの延長線上にあることを危惧している。かつて、これほどまで豊かで濃密な<官能>が精神科臨床にもたらされていたことをもう一度振り返ってほしい。これは精神科医はもとより、一般読者にも願うことである。<官能>が根絶やしになり、臨床の土壌がやせこけてしまったなら、もう後の祭り、決して元には戻らない。いまこそ、中井が臨床の真ん中にいた時代を顧みるべきときである。
熊木徹夫(あいち熊木クリニック<愛知県日進市(名古屋市名東区隣)。心療内科・精神科・漢方外来>:TEL: 0561-75-5707: https://www.dr-kumaki.net/ )
<※参考>
精神科薬物治療を成功に導くために、精神科医・患者双方が知っておくと良いだろうこと
妊婦さんや授乳期のお母さんの、理想的な精神科薬物との関わり方

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

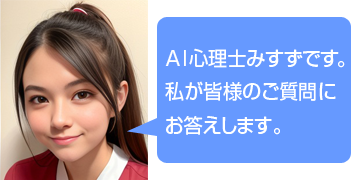

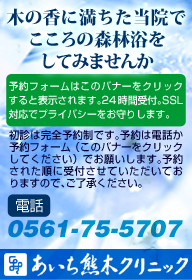



ディスカッション
コメント一覧
この論文、白眉です。わたしも中井先生のこの論文に多大な影響を受けた一人です。『治療の聲』創刊第2号、ぜひ、皆さんも手元に置かれますことをお勧めします。