“服み心地”と「官能的評価」の違い(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
私は拙著『精神科医になる』(中公新書)の中で、精神科薬物の「官能的評価」という用語を持ち出し、こう提唱した。
処方あるいは服用した薬物について、患者あるいは精神科医の五感を総動員して浮かび上がらせたもの、(薬物の“色・味わい”といったもの)や、実際に使用してみた感触(薬効)、治療戦略における布置(他薬物との使い分け)といったもの。
そしてこれを集積することで、おのずから薬物が持っている特性とそれにシンクロする患者の身体構造が浮き彫りになるのだと述べた。ではこの「官能的評価」と、いわゆる“服み心地”とはいかように違うのか。
“服み心地”とは、患者にのみ帰属するものである。患者がそれを自覚し表出することで、完結する。それに対し「官能的評価」とは、精神科医・患者の間主観的体験を言語化したものである。もっというなら、患者の身体に発して、精神科医やその他体外環境(治療の場、および患者の生活環境)との相関関係にまで及ぶものである(言い換えるなら、これは「身体の空間的連続性」を指し示すものである)。
また身体は、時々刻々あるベクトルを指し示しながら、揺れ動いている。「官能的評価」とは、その連続的な揺れ動きを患者自身が感じられることで、初めて表現できるものである(ここには「身体の時間的連続性」が表現されている)。
このように「官能的評価」という、現時点の患者身体に端を発し、精神科医や周辺環境、未来の患者身体といった時空間を超越したところにまで連綿と続く意識の持ち方を想定しなくては、精神科薬物は、ただ単に眼前の患者が表出させる症状に対し、操作的に外力を加えるというものでしかない。
そこで、この「官能的評価」が精神科治療において持つ可能性を探りたい。そして、実際に良質な「官能的評価」をどのように引き出し、それを臨床の場でどのように役立てるか、その方策を講じたいと考える。
<※参考>
良き「官能的評価」がもたらされるための条件(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
そもそも身体感覚の鈍い人とは(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
”主客”の共鳴から生まれる「官能的評価」(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
『精神科薬物の官能的評価 〜精神科医と患者、主観の架け橋〜』

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

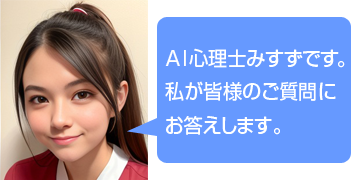


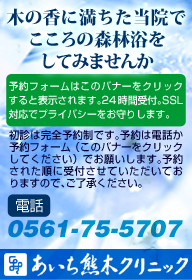



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません