精神科薬物の官能的評価 とは
精神科薬物の官能的評価 とは|精神科医と患者、主観の架け橋
*熊木徹夫 講演録より転載
1:はじめに
本日は、このような貴重な場にお招きいただき、ありがとうございます。
あいち熊木クリニックの熊木徹夫です。
このたびは、これまで私が提唱してきました「精神科薬物の官能的評価」について、その概略を説明させていただこうと思います。
皆さんの日々の臨床現場においても、官能的評価を意識され、その集成・活用に興味をお持ちいただけることがあるなら、幸いと存じます。
もし、これまでに私の著書をご覧いただいたことがある方には、重複箇所が多々あるかと思いますが、官能的評価アウトラインの再確認ということで、どうかご容赦ください。
本日の前半は「薬物は症状にではなく、〈構造〉に効く」ことについて、若干の精神病理学的考察を行い、後半は官能的評価そのものの解説をさせていただきます。
特に前半は「堅苦しい話だな」とお感じになるかもしれませんが、官能的評価の意味と必要性をお伝えするうえで重要なものとなりますので、どうぞお付き合い下さいますよう、お願い致します。
2:臨床の場で初めて受けた衝撃
まず最初に、ある一言を紹介いたします。
「薬物は症状にではなく、〈構造〉に効く」
・・これは、ある日先輩精神科医から聞いた言葉。たいそう衝撃を受けた。
薬物は、症状に対して効くものだというのが世間一般の常識。
ついにその言葉の詳細については聞くことなく今日にいたっている。
この〈構造〉とは何か、その意味を考えてみようと思う。
精神療法に負けず劣らず重要なもう一本の柱・・それが向精神薬による薬物療法です。
臨床をやっている人にとっては当然のことだが、一般的にこのことを知らない人は多いようだ。実は私もそうだった。
臨床現場に足を踏み入れて、その事実に驚かされたのだ。
それまで〈カウンセリング医者〉としての自分の将来を、漠然と思い描いていた。
それは次の理由からである。
「外部から後天的に受けるストレスなどが原因で陥ってしまったこころの不調を修正するには、やはり薬物など外からの物質の投与によったのでは、うまくゆかないはずだ」。
すなわち、こころの治療に薬物はふさわしくないという思いからである。
しかし間もなく、その考えは改変を迫られることになる。
悶え苦しんでいた患者さんが、薬物の服用を境にその苦しみをとかれ、みるみる表情を和らげていったのである。
その劇的な効果を目の当たりにして、薬物の威力を認めない訳にはゆかなくなった。
同時に「これまで悪くなってきた道順を、逆戻りすることでしか良くすることができないわけではない。ストレスから悪化した精神状態だからといって、必ずしもストイックに薬物を使用せずに治そうとすることはない」との思いが強くなっていった。
とはいえ、脳に働きかけるはずの薬物がこころの何かを変えるという事態を、うまく説明できぬもどかしさを胸に抱えていた。
それからしばらくして、先輩医師の行なう良質な精神療法が、患者の苦しみをほどく場面にも幾度も遭遇するようになった。
やはり精神療法はこころに効くのだ。
さらにそういった精神療法は、薬物療法と併行して行なわれているのが常であり、このことにいたく衝撃を受けた。
まるで位相の異なるはずの二つの治療法(薬物療法と精神療法)が、ひとりの患者さんに混合して施行されハーモニーを形作っている。
どうしてこういう事態が起きるのか。
その疑問をかみ砕いて言うならこうである。
精神疾患をこころの病と考えるなら、それにどうして薬物が効くのか。
また、逆にいえば精神疾患を脳の病と考えるなら、それにどうして精神療法が効いてくるのか。
精神科医として働くようになるまでの私には、こころのほうにまずリアリティがあった。
それに対し脳というのは、その実在は疑わぬものの、こころを考える上ではさして必要を感じないもの、ほとんどこころと接点がないものであるような気がしていた。
「こころとは脳の機能の一つ」という捉え方も、無理に理解しようとすればできなくはないが、これはこころの実在を認めない見方であるゆえ、私自身の中でいま一つ腑に落ちなかった。
(脳という構造体がおおもとにあり、それを投射して何かに映し出したものがこころなのではなくて、脳というあり方、そしてこころというあり方は互いに等価なものなのではないかという考えは、その当時まだ浮かんでこなかった)。
こころとは何か。脳とは何か。
この二つはいかなる関係でつながっているのか。
その答えを与えられぬまま、私は臨床のキャリアを積み重ねてゆくことになった。
3:〈構造〉とは何か
そこで先に挙げた言葉「薬物は症状にではなく、〈構造〉に効く」との出合いである。
構造という言葉は抽象的で捉えどころがないにもかかわらず、これまでにあらゆる場であまりに使い込まれてきた。
それゆえこの言葉には、その使い手によってまるで違った意味が付与され、この言葉の与えるイメージはまったくとりとめがない。
だがここで言われている〈構造〉は、もう少し輪郭のはっきりしたものである印象を私はもった。その〈構造〉を論じる前に、先ほどから問題にしている脳およびこころの構造について考えてみたい。
まず、脳構造をモデルとした脳科学の観点から論じることにする。
脳科学とは、脳がさまざまな物質からなる臓器の一つにすぎないという事実に注目し、まず解剖学的構造を知り、さらに生化学的・生理学的に機能を捉えるなら脳というものがわかるとする、人間機械論的な見方に立脚した学問である。
脳科学でいう構造とは、具体的にシナプスや神経化学物質のレセプターといったものを指していると考えられる。
向精神薬の薬理学的作用についての説明は、もっぱらこれに終始する。
たとえば、ドーパミンが増えすぎるから統合失調症になるとか、セロトニンが不足するからうつ病になるといった仮説がそうである。
この説明は一見因果関係が明瞭なだけに、大きな説得力をもつ。
しかし、実際に臨床に携わる私を含めた一定数の精神科医たちは、この明晰なはずの薬理学的説明に、しばしば違和感ととまどいを覚えている。
それは精神科臨床では、患者に生じる現象(すなわち精神症状)と薬物によってもたらされるはずの効果が、非常に複雑で、精神科医にとっても予想がかなり困難なことが多いからである。
それは具体的に挙げれば、以下のようなものである。
同様の精神症状(たとえば、幻覚)をもつように見える患者さんたちに同一の薬物(たとえば、クロルプロマジン)を投与した場合、効果の出方がそれぞれ違ってくること(たとえば、幻覚が消えたり、幻覚の形が変わったり)がある。
また同一患者に同一の薬物を用いる場合でも、時と状況により異なった作用が導かれることがある。
現在主に使用されているいわゆる西洋薬は、おおむね単一物質であり化学構造式も複雑なものばかりとはいえない。
そんな単純であるはずの物質がひとたび生体に取り込まれると、かようにも多様で変幻自在に機能することに驚かされてしまう。
なぜそうなのか。
ここで多様で変幻自在なのは、物質ではなく構造のほうである。
これまで薬理学的作用の説明でも構造の変化(たとえば、SSRIという薬物は、シナプスからいったん放出されたセロトニンという物質が、シナプス内に再び取り込まれるのを阻害するという働きをもつ。
その際、シナプスの構造も変化する)について語られてきているが、この場合薬物の作用の及ぼされる前後のいずれにおいても、そのモデルとなる構造はスタティックな状態にあることが、あらかじめ前提されている。
しかし精神科医たちは臨床現場で、構造は絶えずダイナミックに揺れ動き、また状況に応じて構造の変化のベクトルが異なってくるのを感じている。
薬物療法において、どのタイミングで薬物投与しなければならないかということが非常に重要となるゆえんである。
さらに患者の生体について言うなら個体差が著しいので、その点にも配慮しなければならない。
さらに精神病理学で構造という場合、脳科学で説明される構造とは質的に異なるもので、治療者や患者の間主観性を基盤とした、物質としては捉えられないものを指す。
これは精神構造と呼ばれるものである。
これを、こころの構造と言い換えてもいいだろう。
このように構造といってもかなりの程度、それぞれにおいて意味の差異が認められる。
ではそれぞれの構造同士の関係はどうなっているのか。
たとえば同一の人間の存在の仕方について、脳科学的構造と精神構造というそれぞれまったく別の様式の構造で説明をつけることができる。
すなわち双方の構造説明は、同一人物の中で同時に成立しうるものといえる。
ただ、一人の人間におこる一現象を双方の構造で説明しようとするとき、それぞれの説明を具体的に照らし合わせることは困難であり、時には不可能ですらある。
しかしここでいう脳科学的構造と精神構造は、いずれも冒頭に示した〈構造〉とは違うもののように思われる。
それらはいずれも〈構造〉そのものではなく、〈構造〉がある方法によって映し出された「像」である。
〈構造〉は私たち(精神科医であろうとなかろうと)が直接了解することはできないもので、その投影物を介してのみイメージすることが可能となる。
〈構造〉を地球に比するなら、その「像」は地図(たとえばメルカトル図法によるもの、モルワイデ図法によるものなど)といえるだろう。
では〈構造〉とは何か。
これは、より具体的にあるひとりの人間の存在の仕方を表すもので、存在構造とでも言い換えることができるだろう。
ところで「薬物は〈構造〉に効く」のであれば、薬物の効果を浮かび上がらせることは、逆に〈構造〉のありようを知る一つのきっかけとなりそうである。
すなわち治療者にとり薬物療法とは、単に一治療法にとどまらず、薬を介した〈生体との会話〉なのである。
〈生体との会話〉は、診断をつけることと同義ではない。
診断は、生体とコミュニケーションをとり了解しようとする方法のなかでは、かなり特異な方法である。
通常診断とは、ある生体の状態について多数者が共通了解に達するため、一般的に通用する言葉にあてはめる行為のことである。
それに対し〈生体との会話〉とは、言語表現を通しては到底掬いとれず治療者・患者双方の身体感覚を通してしかわかりあえないような、より未分化で普遍的なものを指す。
〈生体との会話〉は、いかなる治療を行なうにも不可欠なものである。
精神科医は臨床現場で、絶えずそのことを意識し、さまざまな角度から生体に対し会話できるよう、方法を模索してゆく必要がある。
多くの方法をもち、それらから感受されるものを重ねあわせることにより、〈構造〉はその姿をおぼろげながらでも現してくれるに違いない。
4:臨床現場での〈構造〉の取り扱われ方
では現在の精神科臨床で、〈構造〉はいかに取り扱われているか考えてみたい。
先に私は、位相が異なるはずの二つの治療法(薬物療法と精神療法)が、一人の患者に混合して施行され、ハーモニーを形成していることに衝撃を受けたと述べた。
そしておそらく他の多くの治療者も、同じ感じにとらわれたことがあるはずである。
しかし大抵の場合、この衝撃は不問に付せられたまま、各々の治療者のキャリアが積み重ねられてゆくことになる。
実はこの衝撃は、臨床の初心者の潜在意識にある影響をもたらしている。
たとえば、患者がよくなりさえすれば、どんな方法論を援用することも是とする考え方がそうである。
現に先に挙げた薬物療法・精神療法のみならず、集団療法・家族療法といった多数者を介したものや芸術療法・その他さまざまな位相の異なったものが、同時併行的に実施されることはまれではない。
これだけ多くのパラメーター(媒介変数)が存在すると、後にもたらされる結果が何にもとづくものなのか検証するのが容易ではない。
つまり治療状況をコントロールするのに多大な困難が伴うはずである。
しかしこれらを行なうに際し、現在の治療者にそれほどの覚悟があるようでもない。
もとはといえば、精神科で歴史的に形作られてきた治療観が、これらの事態の基底にあるように思われる。精神科では長らく不治と見なされ、悲観的に予後が語られる患者が多くいた。かつての精神科医たちは、悲壮な覚悟で果敢な挑戦を続けてきたに違いない。その流れが今も、治療文化として受け継がれてきているのであろう。
精神科薬物療法に多剤併用傾向が見られるのも、同じ流れからきていると思われる。
多くの方法論を同時に用いることと同様、多剤併用はその状況認識・管理において、一剤のみ用いる場合に比べ数等難しい。
それに対し多剤併用のメリットとして、一剤大量投与によるリスクが回避できるとか、カクテル効果が狙えるといった説が伝えられているが、実情は定かではない。
また薬物の処方に唯一絶対の正解が見出せないことも、試行錯誤としての多剤併用を許容する土壌となっている。
5:〈構造〉把握の感度を上げる
ここまで、精神科臨床では多様な方法論が同時併行的に用いられること、また多剤併用が行なわれやすいことについて指摘してきた。
その背景として、歴史的に精神科医が冒険的姿勢を持ち続けねばならなかったこと、その影響が今にも及んでいることも述べた。
しかし実際の臨床では、恣意的に多くのパラメーターを導入しようとしなくても、必然的に多くの現象を取り扱わねばならないことが多い。
患者の〈構造〉そのものが時々刻々変化を遂げるので、多様な角度からの「像」を治療の手掛かりとして取り出す必要があるからである。
仮に少ないパラメーターの取り扱いにしか慣れていないと、こういった状況は克服できない。
EBMで導き出されたエビデンスが、精神科臨床の現場でしばしば適用不能なのも、このことに起因する。
さらに精神科医は、こういった複雑な状況を切り回すため鍛えられ、結果として〈構造〉把握へむけて感度が高められてゆくことにも注目したい。
治療上多くのパラメーターを同時に取り扱うことは、コンピューターに制御されず操縦士の腕だけで飛行機を飛ばすことに似ている。
空気の流れ・天候・地形などありとあらゆる状況の変化を考慮に入れながら、離着陸・飛行を行なう。
まさにこれぞ臨機応変。
精神科医の中井久夫が『分裂病と人類』の中でいう「兆候空間=微分(回路)的認知」は、統合失調症の特性を示すものであるが、精神科医の治療的営為にもこれが求められている。
では実際にこれらの感覚は、いかにして体得すればよいのか。
向精神薬の効果を浮かび上がらせることは、逆に〈構造〉のありようを知る一つのきっかけになることが想像される。
実際には、薬物と患者をわかるプロセスは同時併行的に展開してゆくため、薬物を知ることは患者を知ることにも通じ、逆もまた真である。
そこで、ここでは薬物療法を例として、以下に〈臨床感覚〉を体得してゆく手順を考えてみたい。
臨床の初心者になった気持ちでスタートしてみよう。
患者と薬物のいずれを知るためにも、まずは薬物を使用してみなければ始まらないが、初心者に適切な使用はおぼつかない。
とりあえず患者の〈構造〉を知る足掛かりをいかにして見つけるか。
そこである薬物を先輩医師に処方してもらい、その前後の患者の変化を比べることになる。
ここでは直接この二人の治療者間で交わされる言語はそれほど重要ではなく、〈生体との会話〉の仕方を体でわかることが重要である。
すなわち、先輩医師が患者の変化に応じて感じ取っている何ものかに、初心者もシンクロしようとすることこそが大事なのである。
やがて薬物は、先輩医師の治療意図を知る上で媒介物の役割を果たすことになるが、やはりそこにも言語はない。
臨床の初心者はなるべく、患者の〈構造〉を簡単に言語で表現する習慣を持たぬようにするのが理想的である。
強迫的に診断や症状の記載を行なっていると、ありのままの〈構造〉を感じることなくわかった気になり、大切なことが抜け落ちてしまうことになるからである。
初めて〈生体との会話〉をするに際し、言語は認知の範囲を決めてしまうという点で、じゃまになることすらある。
次に、先輩医師の診察に立ち会い、その後先輩医師により処方されるであろう薬物の予想を立てる。
薬物と患者相互の〈性格合わせ〉をするつもりで行なう。
これは「兆候空間=微分回路的認知」を鍛えるのに大変役立つ。
もし自らの予想と先輩医師の処方内容が違ったものであったなら、その旨を告げ、先輩医師より処方内容の根拠・是非について意見してもらう。
これを、さまざまな先輩医師に就いて繰り返し行なうことにより、ゆくゆくはそれらの先輩医師たちの診察の場の作り方まで読めるようになる。
こうして初心者は先輩医師の〈目〉を通して、患者の〈構造〉を知る手掛かりを得てゆく。
実際の臨床家の場合、ここまでの過程は、先輩医師と同じ患者に接することのできる最初の数年のうちに行なわれることが理想であろう。
6:うちなる官能的評価の誕生
ここまできてやっと、官能的評価が重要な意味を持つようになってきます。
では官能的評価とどういうものか、具体的に説明してゆきましょう。
そのためには、もう一度、薬物療法を行うための前提に立ち返る必要があります。
実際に薬物療法を行うにあたり、与えられる2つの情報があります。
その一つが、精神科薬物の薬理学的作用についての説明、もう一つが、疫学的(統計学的)データ。これらの情報は、共に重要に違いないです。
これを参照しながらいろんな解釈を行うことができます。
また、特に重要なのは、副作用情報です。
このようなものは、非常に大きなmass(集団)で取り扱われた統計学的データの中から、取り出されるべきものであるので、官能的評価ではなかなか補いきれません。
こういったものの重要性というのは、実際にあると思います。
ですが、精神科薬物の薬理学的作用には、まだ実際は未解明なものが多く、患者さんに用いられた結果から割り出された仮説の域を出ないものも、ままあります。
また、データというのは、疾患別・症状別のグループごとに調べられたものが大多数で、その結果を個々の患者さんの病状に直ちに当てはめられるかということは、はっきりしないことも、踏まえておかなくてはならないと考えます。
結局、薬物というのは“実際に使ってみなければわからない”という、臨床をやっている者であれば当たり前の感覚に逢着するということになります。
ところで、“治療者のうちに今ある薬効のイメージ”というのは何かというと、患者さんの体験を通して、治療者のなかに浮かび上がってきたものです。
その薬効のイメージをそのまま漠然と抱いたまま放置していると、たまたま有効な治療を行えたとしても、それは一度きりのもので、なかなか再現することができません。
例えば料理を作るのに、いろいろな調味料をグチャグチャと入れて作って、たまたまおいしいものができたといっても、もう一度同じものは作れないですね。
ですから、レシピがそのプロセスの中では要るということも、アナロジカルに言えると思います。
さらに、薬効のイメージ自体は、そのままでは時間的・空間的に他者に伝播することができず、その結果、精神科薬物療法の体験を精神科医療全体で集積することも、なかなか上手くいかないですね。
そのためどうしても、投薬・服薬体験の感覚的な部分を、言語化・概念化しようと目論む必要があります。
これが、その人の、あるいは身体のうちなる官能的評価の“誕生”になるということです。
官能的評価は、薬物療法の経験を積めば、自動的に作り上げられてくるというものではないと私は考えます。
うちなる官能的評価を誕生させるためには、相当意識的に薬効のイメージを言語化しようと努めなければならないのではないかと考えています。
7:官能的評価とは何か
では、官能的評価という言葉を、さっきからいろいろ、当たり前のように使っているのですが、これは一体何かということで、一旦見直させていただきたいのです。
これはもともと私が提唱したものです。
具体的には「処方あるいは服用した薬物について、患者さんあるいは精神科医の五感を総動員して浮かび上がらせたもの(薬物の“色・味わい”といったもの)や、実際に使用してみた感触(薬効)、治療戦略における布置(他薬物との使い分け)といったもの」を指して、官能的評価といいます。
「薬物の官能的評価」は通常、臨床家自らが実際に患者に処方し(あるいは自ら服み試し)、試行錯誤を繰り返して行なわれてきているものである。
そしてこれらは、日頃おおっぴらに語られることがあまりなく、各々の臨床家の胸の内に秘められているか、非公式に医局の片隅などにおいて呟きあわれているものである。
ちなみに「薬物の官能的評価」が、EBMにもとづくエビデンスと比較して決定的に異なるのは、前者のうちに治療者・患者の主観が大きく介在している点である。
「兆候空間=微分(回路)的認知」はこれらの介在なくして成立しない。
すなわち、エビデンスだけでは〈構造〉把握の手掛かりをつかむことはできない。
〈構造〉把握の感度を上げるプロセスを経た後に、これまで未知であった薬物の「官能的評価」に触れることにより、治療者は新たに治療を展開する際の有力な足掛かりを得られるだろう。
8:3種類の官能的評価のそれぞれの役割とは
ところで官能的評価とは、何でもかんでも、一緒くたにできるかというと、そうではなくて、それを語る立場によって3種類あると、私は考えています。
(1)服薬体験をした人(精神科の患者さんが主)によるもの
(2)投薬経験をした人(精神科医が主)によるもの
(3)服薬・投薬ともに経験した人(自主服薬を行う精神科医)によるもの
各々の違い・問題点について、簡単に触れたいと思います。
(1)患者さんが自らの身体構造の問題点を感受し、言語で抽出することには限界があり、また、各精神科薬物の特性も、簡単に言い尽くせるようなものではない。
すなわち、“自身の身体構造を感受すること”には、独特の困難があるため、これだけでは、完全に官能的評価を言い尽くすことはできないと思います。
(2)次に、身体の持ち主でない精神科医が、患者さんの主観的体験に相即することには限界があり、どこまでいっても“遠隔操作”をしている感は否めないのではないかと思うのですね。
(3)そこで、自主服薬を行う精神科医についてですが、
彼らが(1)・(2)を橋渡しするキーパーソンとなるのではないかと。
自主服薬することは結構重要なのではないかと考えていますが、しかし、近年このような精神科医はかなり少なくなっているということが、事実挙げられると思います。
9:すぐれた官能的評価とは
続いて、すぐれた官能的評価とはどういうものか、ということで、いくつか列記してみたいと思います。
官能的評価というのは、主観的なものなら何を言ってもいいと考えるなら、そのことについては言及されなくなってしまうのですが、やはり、質の善し悪しはあるはずです。
それは一定量の官能的評価に触れた方々であれば、おそらく誰しも感ずるところだと思うのです。
その質の善いものとは、どういうものかと言うならば、一応次の4つが挙げられます。
(1)同調性の高いもの
ある薬物について、これまでうすうす感じてはきたものの、うまく言語化できず捉えがたかった感覚を、きわめて精細に表現している、と感じられるもの。
「言い得て妙」というようなものです。
こういうものにより、確実に、その薬物による“治療文化”が伝承されます。
(2)“感化力”がすぐれているもの
こういう言葉があるかどうかわかりませんが、感化する力が優れているもの。
これは滅多にないと思います。
天才肌の人物が、天啓のごとく感受し、爆発的に伝藩されていくものです。
これまでの治療の常識がドラスティックに書き換えられ、新たな治療文化が掘り出されるというのは、まさに“感化力”に優れるものだと感じます。
(3)専門家の間で広く共有されているもの
「エキスパート・コンセンサス」と呼ばれていますが、いわば“官能的評価の横断的共有”です。これはこれで重要だと思います。
(4)特別な技法として言い伝えられてきたもの
漢方の口訣(くけつ)がその代表例だと思います。
どういうものかというと、大家が行っていた名人芸のようなものが、本人あるいは門人の言葉を経て伝承されてきたもの。
これを先ほど言いました“官能的評価の横断的共有”に対して“官能的評価の縦断的共有”といえます。
10:官能的評価を収集する社会的意義
官能的評価が精神科医や患者さん個人のうちで、どのように成り立ってゆくかについては、すでに先にお話しました。
しかし、ただこれらの官能的評価がずっと個人のうちに眠っていては、精神科治療文化の発展に寄与することは永遠にありません。
ひいてはユーザーの利益になることもありません。
では、技や感覚の伝承をするためにはどうすればいいのか。
まずは、各々の官能的評価を、陽のあたる場所へ出してやらねばなりません。
それも各々が比較検証される場所へ。
そこで必要なものの一つが、ウェブ掲示板になります。
そのために私は、拙著『精神科医になる』で官能的評価収集の意義を説く際、自らがウェブサイトを用意し、その中で官能的評価に関する掲示板を立ち上げることにしました。
www.dr-kumaki.sakura.ne.jp/protect/bbs3/wforum.cgi
そちらを見ていただくと分かりますが、不特定多数の参加者が、各々の精神科薬物について、自由に官能的評価を書き込めるようになっています。
そして、書き込まれた官能的評価に対し、レスポンスをすることもできます。
具体的に書き込んでいただくことをお勧めしている内容は、次の二点です。
(1)その薬物自体の特徴(服んだときの身体での感じ方)
(2)類似薬物との違い
本当は複雑精妙で、個々人により表出に大きな差があるであろう官能的評価を書くにあたって、これほど単純化することを提案したのには、理由があります。
(1)書き込みという行為への抵抗感を減らす。
(2)書き込み同士の比較対象を容易にする。
これにより、ナラティブ(精神科医や患者さんなどの語り)を集積し、非常に強力なデータベースを作ることができるのです。
そして書き込みの集積は、やがてその薬物についてのコンセンサスを生み、精神医療自体を変える力を持ちうるはずです。
ただし、情報はやはり量より質です。
数多ある書き込みの中から、とりわけ訴求力のあるものを抜き出し、そのものの持つ素材本来の味を生かして、さらに独自の味付けを施すことにより、新たな気づきをもたらす。
それこそ、私が発行するメールマガジン『精神科薬物の官能的評価〜感じるままに薬を語ろう〜』の編集において、常に目指していることです。
そして、メールマガジンという媒体を通して、情報提供者とその情報の受け手の両者が成す間断ない情報交換こそが、それらの情報自体に洗練をもたらすのです。
また精神科薬物の官能的評価を、同じ薬物で治療を受けているその他の人々にフィードバックするこのシステム(掲示板とメールマガジン)に参加してもらうことにより、その参加者である患者さん自身の精神医療への関わりのかたちは、大きく変化する可能性を秘めています。
すなわち、処方された薬物をただ服むのではなく、あらかじめ官能的評価を下すことを想定して服用するなら、治療は、単なる受身のものではなく、自らが積極的に関わっていくものだという自覚が生まれてきます。
これは、これまでの治療にあっては、あまり意識化および方法化されることのなかったものではないでしょうか。
官能的評価を発信することにより、患者さん自身がより深く精神医療を知ることになるかもしれないのです。
近頃お題目のようによく唱えられる「患者さん本位の治療」とは、具体的にはこのようなかたちをとるものでなければならないと考えます。
さらに、先述した掲示板とメールマガジンをめぐる情報循環システムとは、すなわち精神科臨床における一つの運動とでもいうべきものです。
言うまでもありませんが、ここで表されるものは、各薬物の官能的評価という”定見”ではなく、”経過報告”と考えていただいた方がいいです。
運動は今後も引き続いていきます。
官能的評価に唯一解があるわけではないのですから、今後もこの掲示板に書き込んでいただき続けることが必要です。
“官能的評価の情報循環システム”としては他にも、専門家同士がコンセンサスを作りあうことを目的とした、「複数の精神科医によるワークショップ」などが挙げられます。
官能的評価に一家言ある精神科医が複数集まり、各々の官能的評価を持ち寄って、参照しあい、議論をつきつめ、ある一定のコンセンサスにたどりつくということです。
実際にそれをを試みたのが、一昨年、神田橋條治先生・兼本浩祐先生らとおこなったワークショップです。
「精神科薬物治療を語ろう〜精神科医からみた官能的評価〜」という名で、本にもなっていますので、ご参照いただければ幸いです。
これに留まらず、今後も多くの精神科医の方々に、官能的評価のワークショップを行っていっていただきたいというのが、私の強い願いです。
そして、このようなことを長年続けていけば、xy=1のグラフが永遠の先で限りなくx軸・y軸に近づいてゆくように、ある一定のコンセンサスに至りうるのではないか、と微かな期待を抱いています。
11:各薬物の治療文化を、次世代に伝承するという使命
さらに提言しておきたいのですが、官能的評価収集の隠れた目論見は、いまや”絶滅危惧種”になってしまった数多くの精神科薬物についてのコンセンサスを再生させることにより、これらの薬物を救済し、おのおのの精神科薬物が担ってきた治療文化を根絶やしにしないことにもあります。
おおげさに聞こえるかもしれませんが、これはいまいる精神科医の社会使命だと私は考えています。
「いまよく使われている薬物こそが最良であって、滅びゆく薬物は自然に淘汰されるのだからしかたない」との考えは、精神科薬物に関しては当てはまりません。
一度滅びた薬物は二度と復活しないのです。
それは、使われないようになることで、その薬物の治療文化が根絶やしになり、精神科医がその薬物についてかつて保有していた”記憶”を失うこと、そしてそれにより、実際使用量が激減し販売中止に追い込まれること、これら二つの理由によります。
世の中には、”ほかならぬこの薬”でしか助からぬ人がいます。
長年”ほかならぬこの薬”で、かろうじて社会適応を保ってきた人が、”この薬”が社会から消えたことにより、適応不能になったケースを、私は自分のそれほど長くはない臨床経験のなかでも、苦い思いでいくつも見届けてきました。
このことは将来にわたっても、助けることができるはずの人を助けられなくなる可能性があることを示唆しています。
古い薬物にもいいものはたくさんあります。
その傍証として、精神科最古の薬物クロルプロマジンやイミプラミンなどが挙げられます。
その陰で消えていった薬物には、大きく分けて2種類のものがあるでしょう。
一つは消えるべくして消えていった粗悪な薬物、もう一つは有用な個性を持っていたものの、それが理解されず、あるいは知識として共有されず、不遇な最期を遂げたもの。
前者についてはともかく、後者は消してはなりません。
そのためには…簡単なことです。
声をあげ、次世代に治療文化を伝承しましょう。
皆さんのその言葉こそが、精神医療をやせさせない強力な一助になることを、どうか気づいていただきたいのです。
12:個々の臨床における官能的評価の意義
最後に、個々の臨床における官能的評価の意義についても触れておきましょう。
臨床の場で取り交わされる精神科薬物は、単なる化学物質ではなく、精神科医と患者さんとを橋渡しする大切なコミュニケーションの道具だともいえます。
精神科医は、ある薬物Aに対し一定の官能的評価を有しており、それをもとに薬物Aを患者さんに処方し、治療の方向性を指し示そうとします。
薬物の処方に、治療の意思を仮託するわけです。
その処方を受けた患者さんは、精神科医の発する言葉から、あらかじめ薬物が指向するであろう方向を知り、それをガイドにして服薬に及びます。
そして実際の連続的な服薬体験を通して、体がどの方向に向かうか、その感じ方を探っていくことになります。
その結果、患者さんの側にも、薬物Aに対する官能的評価が醸成されていくことになる。
この精妙なプロセスを司るに際し、官能的評価という薬物にまつわる”言葉”が非常に大きな援けになります。
官能的評価が、薬物療法においての精神科医=患者間の掛け合いに、豊かな意味を与えるのです。
精神科薬物の処方には、本来薬効以外の何ものかが含みこまれています。
それは、薬物療法を行うに際して絶対に必要なものです。
官能的評価は、精神科医と患者さんの双方に「薬効以外の何ものか」への気づきを促す大切なものと成りうるのです。
<※参考>
良き「官能的評価」がもたらされるための条件(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
そもそも身体感覚の鈍い人とは(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
”主客”の共鳴から生まれる「官能的評価」(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)
”服み心地”と「官能的評価」の違い(論文「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」より)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

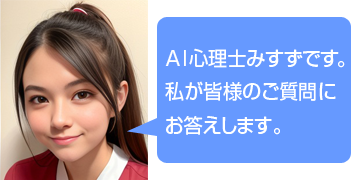

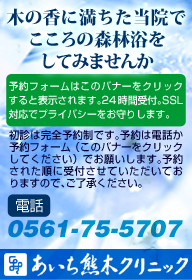



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません