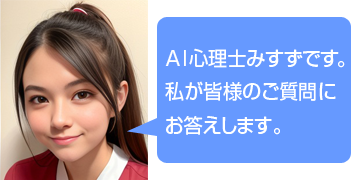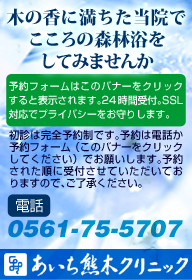「薬物のばらまき」はなぜ起こるのか ~<身体感覚>を導きの糸として~
近年、精神科薬物(向精神薬のこと。以下、薬物とする)をめぐって様々な問題が起こってきている。なかでも、薬物の不正な流通は由々しき問題である。複数の精神科病院やクリニックで「薬物のばらまき」があるとされ、また病院経由ではなくインターネット経由で、依存傾向の強い薬物が売買されているらしい(これには海外からのルートまである)。
この「薬物のばらまき」についてであるが、個別の事象としてはかなり多様な事情がその背後にあるであろう。しかしここでは、できるだけマクロで見ることとしたい(ただし、これは統計的にうかがい知れたことではなく、私の日頃の精神科臨床において、強く実感されることから抽象しようとするものである。その点につき留意されたい)。“ばらまき”という表現には、その主体である精神科医にのみ責任の所在があるような響きがあるが、実は精神科医側のみならず、処方を受け入れている患者の側にも問題があり、それらが複合して関与しあっているのではないかと考えられるのである。そのため、まずは<精神科医側の問題><患者側の問題>と分節して考えてみることにしたい。
<精神科医側の問題>
(1)モラル・職業意識の欠落
薬物という重大なものの処方を司っているという自己認識が乏しい精神科医がいる可能性がある。薬物、とりわけ向精神薬は劇薬であり、専門的判断のもと厳重に管理されなくてはならないのはいうまでもないことである。しかし、精神科医ひとりあたり担当している患者数が膨大なものとなっている現在、薬物処方に対して払われるべき配慮が希釈されるようなケースが増えてきている懸念がある。
(2)薬物処方技術の不足
薬物をばらまく気はないのだけれども、眼前にいる患者の症状の改善に気を取られ過ぎて、ついつい薬物を重ねてしまう精神科医がいる。木を見て森を見ず、近視眼的すぎて長期展望がもてないということである。また、薬物を盛るのは簡単だが、引く方は数段難しい。薬物を盛っていくと、その分量に応じて、患者の生体にはホメオスタシス(恒常性)が生じ、たった一粒の薬物でさえ引くに引けない状況になることがある。例えるなら、複雑に積み上がった将棋の駒の塊から、それらを崩さずに駒をひとつ抜き出すようなものである。そのことを理解した上で、きちんと戦略を立ててやっていない。アクセルを踏むばかりで、ブレーキを踏む技術が備わっていない可能性がある。
(3)<身体感覚>の鈍麻
患者の<身体感覚>(自らの身体へ及ぼされる力を、適切に感受したときに芽生える感覚)への了解や配慮を欠くほど、精神科医自身の<身体感覚>(自らの身体を映し鏡にして、患者の身体の有りようを感受するときに芽生える感覚)が根本的に鈍くなっている可能性がある。「よりによって精神科医が、自らの身体に対して鋭敏な感覚を持たねばならないなんて!」という向きがおられるかもしれないが、精神科医といえど、薬物療法が単なる“患者身体への遠隔操作”であっていいはずはない。薬物療法においては、治療者と患者、双方の<身体感覚>が絡み合うのであり、それが双方に自覚されねばいい治療とはなりえない。
<患者側の問題>
(1)薬物情報の拡散
インターネットなどを中心に、薬物についての情報が、広くおおやけになったということがある。ただし、それらは玉石混淆で、また受け手である患者がどのように捉えているか見当がつかないことがある。情報の流れやその質は、誰にも制御できない。
(2)薬物に対する警戒心の欠如
薬物の情報があまねく行き渡ったことを受けてか、薬物が安易に求められ、手軽に服用される流れができつつある。また医師の手を介さずに、インターネットなど経由して患者が直接に薬物を入手することなども起きてきており、薬物に対する恐れの感情が麻痺してきていることも問題である。それにより、薬物という身体に強大な力を及ぼす物質に対して、本来人間が備えていたであろう警戒心が緩んできているかもしれない。
(3)<身体感覚>の鈍麻
自らの身体の危機を感知し、その官能を通したモニタリングが十分に出来ていない、言い換えるなら、患者自身の<身体感覚>が鈍いことも多くなってきている。それにより「嗜薬」(筆者の造語。身体の自然な要請に関わりなく、薬物を漫然と自己身体の内に取り込む快楽の伴う癖)が生じやすくなっている点にとりわけ注意を払う必要がある。
ここで<身体感覚>という言葉が出てきたが、私はこの言葉が、精神科臨床においての薬物を巡る様々な事象を理解する上で、極めて重要なキーワードになると考えている。そのような事象のいくつかを取り上げ、その因果について簡単な説明を企ててみたい。
例えば、薬物依存の患者が、方々の医療機関で症状を偽ってまでも、欲する薬物の取得にいそしむ姿が見受けられることがある。また、それとは逆に、精神科病院やクリニックにおいて正規に処方された薬物に対してさえ、嫌悪感をむきだしにし、忌避するようなケースも増えてきている。この二つは、薬に関する関わり方としては、一見まるで違うものであるかのようである。しかし私は、実はこれらが同じものの表裏じゃないかと考えている。薬物を自分の<身体感覚>に合わせて服む習慣がそもそも備わっていない、つまり<身体感覚>の鈍い人であるという意味では、どちらも変わりがない。そもそも、身体の言うことも聞かずに自分の欲の働くままに薬を取り込んでいくという態度と、身体に薬物というものを取り込むということを端から忌み嫌って排除するだけの姿勢とは、身体を阻害しているという点においては何も違いはないのである。
さらには、依存症について考えてみたい。薬物依存になる人の<身体感覚>はやはりおしなべて鈍い。ただ大切なことは、<身体感覚>が鈍いのは処方される患者だけではなく、処方する側、すなわち精神科医も同様に<身体感覚>が鈍いことが多いという点である。そのため薬物依存については、依存する側の患者の病理に帰せられることがもっぱらではあるけれども、実は精神科医と患者の合作なのだと考え直す必要がある。
では、<身体感覚>を研ぎ澄まし、その結果かつて人間が抱いていた薬物への恐れと身体への畏れを取り戻すために、日頃どのようなことを心掛けてゆくべきなのか。自分の身体が、神か仏か、とにかく何か大きなもの(これは何らかの宗派を問うものではない)から借り受けた大切な器で、この世を去る時にはその器をきれいにして返さなくてはいけないと考えて信じることができるかどうか、これがカギになってくるだろう。常に身体に支えられて生かされているという感謝の気持ちを持ち続けることができるのであれば、身体を本当に大切に取り扱うことができるはずである。<身体感覚>は、そのような心持ちでよく手入れされた心身に宿るものであり、これは一朝一夕で出来あがるものではない。
また心気症の人のように、身体の滅びのような感覚にみだりに襲われるというのは、<身体感覚>が鋭いとの誤解を受けやすい。しかし身体からのシグナルに過剰に反応するのは、身体からのシグナルを無視するのと同様で、真の意味で<身体感覚>が鋭敏であるとは言えない。
今後の精神科臨床を退廃させず、意義ある営為として存続させてゆくため、精神科医と患者ともども、自らの<身体感覚>の有りようを感受し、精神科臨床の場を豊かな官能で満たしてゆくことこそ肝要である。これは、いかに精神科医療が先進的になり多様な薬物が使われるようになったとしても、普遍的に引き継がれてゆくべきことなのではないだろうか。
熊木徹夫
(あいち熊木クリニック<愛知県日進市(名古屋市名東区隣)。心療内科・精神科・漢方外来>
TEL: 0561-75-5707 )
*熊木徹夫のYoutubeチャンネル『うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!』では、記事の要点や、追記にあたる説明を、熊木徹夫自身が解説しています。
ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
大切なのは薬物への怖れと身体への畏れ|うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!
<※参考>
「らしさ」の覚知とは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
臨床現場、混乱の原因となるものは(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)
初診時における精神活動(論文「「らしさ」の覚知 ~診断強迫の超克~」より)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707