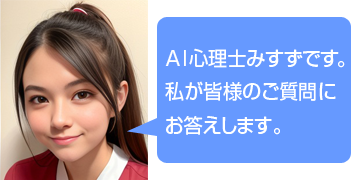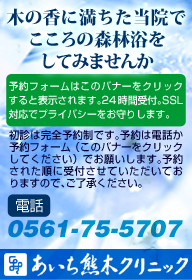「官能的評価」から考えた精神科治療論~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか・2~
(熊木徹夫論文・『こころの科学』所収)より一部改変掲載
6:めざすのは「快」ではなく「楽」
薬物療法において最終的に目指すべきなのは、「快」ではなく「楽」である。
薬物選択にあたり、極めて重要なことがある。それは「「楽」をもたらす可能性の高い薬物を、治療の中心に据えよ」ということである。治療において「快」が全くあってはいけないとはいわないが、それらは一時的・限定的なものであるべきである。また精神科医・患者さんとも、「快」の発現に対し、自覚的であるべきだ。
ここで、「快」と「楽」のその違いについて触れておきたい。「快」とは、そのあまりの心地よさのため、耽溺し、強く執着するような状態を指す。すなわち、身体がある物質や行為を欲し、とめどなくなるような状態のことである。それに対し「楽」とは、苦のない状態のことである。”特に耳をそばだてた時のみ、身体が何かをささやいてくる状態”とでも表現するのが良いか。「楽」の訪れは、刺激に乏しく、なかなかその自覚を持ちにくい人も多い。
「快」を伴う薬は、劇的に状況を打開することがままあるため、精神科医・患者さんともその処方・服用の誘惑に駆られやすい薬でもある。しかし、それは諸刃の剣であり、治療において破壊的に働くこともままある。精神科医・患者さんとも、このことに絶えず注意を払うべきである。
身体的・精神的依存を伴う薬は、基本的に「快」をもたらす薬である。このような薬物は、一過性に頓服処方するのが望ましい。やむをえず用いなければならない場合には、患者さんに、この薬物が依存を引き起こす可能性をあらかじめ説明しておく。そして、依存誘発の危険があるにもかかわらず用いるべきだと考える理由、これは一過性に用いるべきものであるから、いずれ離脱を目指すが、その離脱に向かうタイミングは精神科医が責任を持って指し示すつもりであることなど伝える。精神科医は、ランディングポイントを常にイメージしておくことが大事である。ただ、あまり患者さんを怯えさせては投薬できなくなるので、その塩梅は難しい。
多くの感情調整薬は、「楽」をもたらす薬物に分類できる。これらの薬物には如実に分かる服薬感がほとんどなく(よって官能的評価も形作られにくい)、患者さんとしては今ひとつ服み応えに欠けるものであることが多い。そのため、患者さんが自然離脱してしまう危険が大きく、安定期を維持することが難しい。ゆえに、長期的な治療ビジョンを指し示し、それを納得・共有してもらう必要がある。
7:抗うつ薬における「快」と「楽」
最後に、抗うつ薬を精神科治療においてどう位置づけるべきか、「快」と「楽」の視点から考えてみたい。
私は、抗うつ薬とは、その患者さんにとり、まず「快」を引き起こす薬物か、「楽」を引き起こす薬物かで、大きく分けて考えるべきものだと考える。抗うつ薬の「快」とはすなわち、意欲亢進・明朗快活化の作用である。まず「快」を引き起こしやすい薬物の例として、アモキサン・パキシルなどが挙げられる。それに対し、抗うつ薬の「楽」とは、抗不安・鎮静・鎮痛作用である。まず「楽」を引き起こしやすい薬物の例として、デジレル・テトラミドなどが挙げられる。
例えば、抗うつ薬で発動性が上がり、嫌なことでも難なくできるようになる場合について。これは「楽」になったのではなく、「苦」を麻痺させているため、身体のたがが外れてしまっているのである。すなわちこの抗うつ薬の作用には、「快」の要素が大きい。日本社会では勤勉であることが貴ばれ、大方の労働者に労働強迫があるので、痛痒なく就労できるようになる「快」をもたらす抗うつ薬が、好んで服まれる傾向がある。しかし、その場合”体力の前借り”をしているため、そのツケが後で回ってくる。このような「快」の要素が大きい抗うつ薬には、退薬症状としての不安・焦燥がつきものであるが、これは「浦島太郎が玉手箱を開けて、一気にお爺さんになってしまうようなこと(竜宮城でのかりそめの享楽に身を置くうちに、自覚なきまま老いていた現実に一気に引き戻されること)」ととても似ている。
「楽」を目指す抗うつ薬は、活動レベルを下げて、良質の眠りを与え、”身体から疲れを絞り出す”薬物である。疲労が色濃く滲み出ているうつ病患者さんの場合、第一選択はこちらであろう。私は患者さんに、うつ病治療の要諦は「一に睡眠、二に睡眠、三四がなくて、五に食事」だと伝えることが多い。しっかり眠りを得られた身体からは、自己治癒力を引き出すことができる。これは、一度沈めて、身体にほとんど余計な負荷をかけないようにしてから、身体が勝手にじわじわ持ち上がってくるのを待つ薬なのである。
さらにその後、しっかり力をためてから、さらに持ち上げてくる際に、「快」をもたらす抗うつ薬を慎重に用いるのであればよい。ただ、このような抗うつ薬は、処方量といい、そのタイミングといい、うまく使いこなすことは難しいので、それほど治療経験が多くない精神科医は手を出さない方がよい。原則として、それ以外のおおよその薬物を試し、どうにも閉塞状況から抜け出しがたいという時に、慎重を期して少量ずつ増やしていくべきものである。また原則として、双極2型障害の抑うつ状態では用いるべきでない。
こうして見ると、抗うつ薬は何も精神科薬物において特別なものではない。患者さんの深い納得のもと薬物処方を行い、患者さんの身体を耕し、良き「官能的評価」を生み出し、自己治癒力を引き出す。そして、薬物から離脱したあかつきには、病状が再燃しにくい身体感覚を恒常的に維持できることを目指す。精神科薬物療法とはつまるところ、そういうものなのである。
*熊木徹夫のYoutubeチャンネル『うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!』では、記事の要点や、追記にあたる説明を、熊木徹夫自身が解説しています。
ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
めざすのは「快」ではなく「楽」|うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707