「都会のど真ん中にある精神科病院でその気配さえ感じられぬ病院」が孕む問題
こんにちは、熊木です。
水谷雅信先生の文章に触れて、ふと思い出したことがあります。
私は彼の沖縄時代の話が大好きで、どんな話も常に興味津々で聞いてきました。
それは、沖縄以外の日本で精神科臨床に携わる者達の”常識”を軽く打ち破るもので、聞くと唖然とするものの、後に痛快さが尾を引くような感じがしたものでした。
一方、私はその頃、自分の勤務する大学病院・精神科病院以外にも、先輩精神科医から紹介され、比較的多くの精神科病院の当直をする機会に恵まれていました。
そのほとんどが愛知県、それも半径20kmくらいの領域に収まります。
しかし、それぞれの“病院文化”があまりに異なることに驚きました。(その詳細は、機会を改めて、書くこととします)
ここでは一点のみについて触れます。
それは「都会のど真ん中にある精神科病院で、その気配さえ感じられぬ病院は、いろいろと問題を孕んでいることが多い」ということです。
田舎(といっても愛知県郊外)の病院は比較的のどかで、入院患者さんが畦道を散歩したり、自転車で往来しても、まわりの皆が寛容で、時には声をかけてくれたりします。
私も患者さんと散歩をしていたら、近くの農家の方がトマトをくれたりしました。
そのような病院でも、もちろん閉鎖病棟はありますが、“原則開放”なので、不必要な閉鎖的措置は少なくなる傾向があったように思います。
一方、私は当直に訪れたときに、「こんなところに精神科病院あったっけ?」(これまで、この付近を何十回も車で行き来しているのに、その気配さえ感じたことがなかった)と感じるようなところは、中に入って、いろいろと驚くことが多かった。
まず最初に、「あまりの静けさに、気味が悪いな」と感じました。それなら、患者さんの状態が皆いいのか、というと、そうでもない。
ただ、看護師さん達が、異様に規律正しく、患者さんに対し点呼を取っていたのを覚えています。ある看護師さんと当直の夜に話したら、こうぼやいていました。
「この付近は、昔はイノシシがいる田舎だったけど、いまではすっかり新興住宅地になってしまって、患者さんが大声でも上げようものなら、怒鳴りこんでくる人がいる。近頃は、患者さんを気味悪がる人も多く、散歩に連れ出すこともできない」
なるほど、それだから、この病院は“原則閉鎖”なのか。(ここの“開放病棟”は、田舎の精神科病院の閉鎖病棟に酷似しており、またここの”閉鎖病棟”は、まるで隔離室のようでした)
私たちが精神科医になる前の時代、精神科病棟の“人権侵害”を弾劾する流れがあり、その暗い陰を見ずして、精神科医にはなれない雰囲気がありました。
“精神科医は、「精神科患者さんを治し、幸せにしたい」と考える人ばかりがなるはずであるのに、どうしてそのような精神科医が中心となって管理している精神科病院にこのような暗い話がつきまとうのか”――当時医学生だった私は、素朴にそう感じ、首をかしげていました。
しかし、精神科医療のインサイダーになった直後に垣間見たものから、ひとりの精神科医・ひとりの看護者の力ではどうにもならない強い力がほうぼうにあることを思い知らされました。
同じ時期、沖縄の精神医療の在り方に瞠目した水谷先生が報告してくれた様々な興味深い事柄から、都市部の精神科病院がなぜ、進めるべき開放化とは真逆の方向に行かざるをえないのか、その理由が了解できました。
すなわち、沖縄に今もある「しなやかで強靭な地縁」が失われ、「隣人に対する不信と猜疑に満ちた、殺伐・荒涼たる人間関係」が、都会の精神科病院のみならず、都会そのものを蝕んでいたのです。
もちろん、このことだけがすべての不具合の原因ではありません。
しかし私は、「”私とは何の縁もない”はずの精神科病院の在り方が、私のこころの在り方を投影しているかもしれない」という少し意外なものの見方から、初めて見えてくるものがあるのではないか、と考えます。
<※参考>
書評『心はどこまで脳なのだろうか』(兼本浩祐著:医学書院)(雑誌「こころの科学」より転載)

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707

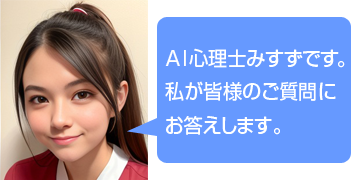

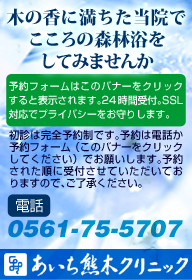



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません