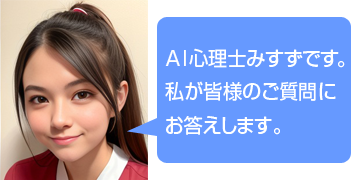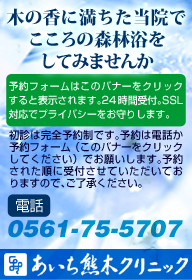「官能的評価」から考えた精神科治療論~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~
精神科薬物療法では、薬物を症状に働かせることを狙うのではなく、患者さんの身体構造を改変し、患者さんがより過ごしやすい状況を恒常化させることを狙う。また、薬物と言葉により、患者さんの身体を耕すことを目指すのでなくてはならない。
しかし、薬物という他力で支えることのみを目指すのは決して理想的ではなく、薬物という“杖”を得て、患者さん自らが立ち上がり歩くこと、いわば患者さんが自力を培うことを幇助することを目指すのが理想である。換言するなら、精神科薬物療法は、“薬物を介した精神療法”でなくてはならない。そのためには患者さん自らが、身体で感じ、考えることが何よりも大事なのである。それにより、患者さんの身体を操作するのではなく、患者さんの身体を介して精神科医・患者さん双方の身体感覚を醸成していくことができるようになる。
ここでは、このような“理想的”薬物療法を展開させるための、「官能的評価」炙り出しの鉄則について述べたい。
体内環境(いわば“身体”のこと)と体外環境(いわば“環境”のこと)を同時に変えてはならない
パラメータ変更は、一度につき原則1つ(多くとも2つ)に留める
例えば薬物であれば、一回につき、一つの薬物の量を増減するだけである。そうしないと身体が大きな変化(症状や副作用)を見せたとき、何がその原因となっているか、同定することが非常に難しくなる。
「身体モニター法」を意識し、身につける
「身体モニター法」とは、平たく言うなら「身体の状態の善し悪しは、翌日の朝の体に訊け」ということである。当日の夜の体は“嘘”をつく(興奮などしていると、身体の状態の適正判断ができない)。
ある朝、体がぐったり疲れているならば、前日にやった何かが良くない。このようにフィードバックし、恒常的に身体の安定状態を築いていく。これは、精神科薬物療法のみならず、生活のあらゆる事柄に応用できる。また、様々な心身の疾患を引き起こさないで生き続けていくため、すなわち養生のための大切な心得である。
投薬・服薬過程には、3段階がある(a.変薬期→b.安定期→c.減薬期)
a.変薬期:
身体の恒常的安定に向けて、増薬・減薬・変薬を緻密に積み重ねていく。
b.安定期:
ほとんど薬物を変えず様子見の時期。何も見るべきところがないように見える時期だが、実は身体に一番重要な治療効果がもたらされるのは、この安定期である。
しかし、患者さんはこの安定期の「停滞感・退屈感」に耐えられないことがある。それに耐えてもらうため、しかるべきときに服薬・投薬過程の3段階を説明し、現在どの段階にいるのか伝えていくことが重要になる。もし「いつまで治療が続くのか(いつ治療が終結するのか)」と説明を求められたら、「そのタイミングは、身体が自然に教えてくれる」ことを伝える。
私は、「精神科医が意図的に治療期間を決めることはできない」と考えている。減薬期への移行の指標は、“昼夜問わず襲う絶え間ない眠気”である。このような眠気が現れたなら、それは「もうこれほどの薬物は要らないよ」という身体からの“薬物お役御免”のサインであり、安心して減薬を開始できる。
c.減薬期:
“昼夜問わず襲う絶え間ない眠気”を指標として、それがなくなるまで、漸減(ゆっくりの減少)を繰り返していく。その結果、全ての薬物を抜き去れれば、精神科薬物療法は一旦終結となる。
精神科医は、この減薬期に、とりわけ細心の注意を要する。患者さんからの減薬の要請が強いからといって、減薬を急ぎすぎてはならない。それは得てして、“ゴール間近の事故”につながる。最後の1錠を抜き去る時に、最も慎重にならなくてはならない。1/2錠、場合によっては1/4錠まで刻んで、そこから無くしきることさえある。あくまでソフトランディングを目指さなくてはならない。
またこの3段階を経過した後、変薬期前(発病期)と同じ地点に降り立つのではない。もしそうだとしたら、また同じような病態が容易に再燃されてしまう可能性が残されてしまう。病む前とは違った、より安全な地点(患者さんが服薬なしでも自律的に健康状態を維持し、再び病的な状態に崩れていきにくい)に着地するイメージである。
「「官能的評価」から考えた精神科治療論 ~いかに抗うつ薬を、服み効かせるか~」
(熊木徹夫論文・『こころの科学』所収)より一部改変掲載
*熊木徹夫のYoutubeチャンネル『うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!』では、記事の要点や、追記にあたる説明を、熊木徹夫自身が解説しています。
ぜひ、チャンネル登録をお願いします。
サインは“昼夜を問わず襲う絶え間ない眠気”!|うんぷてんぷ : 精神科医・熊木徹夫に訊け!

精神科医。
精神保健指定医・精神科専門医・日本精神神経学会指導医・東洋医学会(漢方)専門医
あいち熊木クリニック 院長
心療内科・精神科・漢方外来|愛知県日進市(名古屋市名東区隣)
TEL: 0561-75-5707